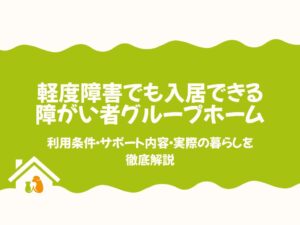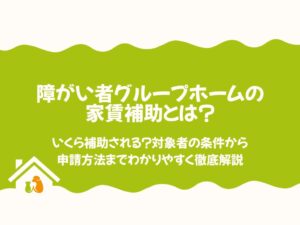障害福祉サービスにおける、障がい者グループホームの役割|「共同生活援助」の基本をわかりやすく解説
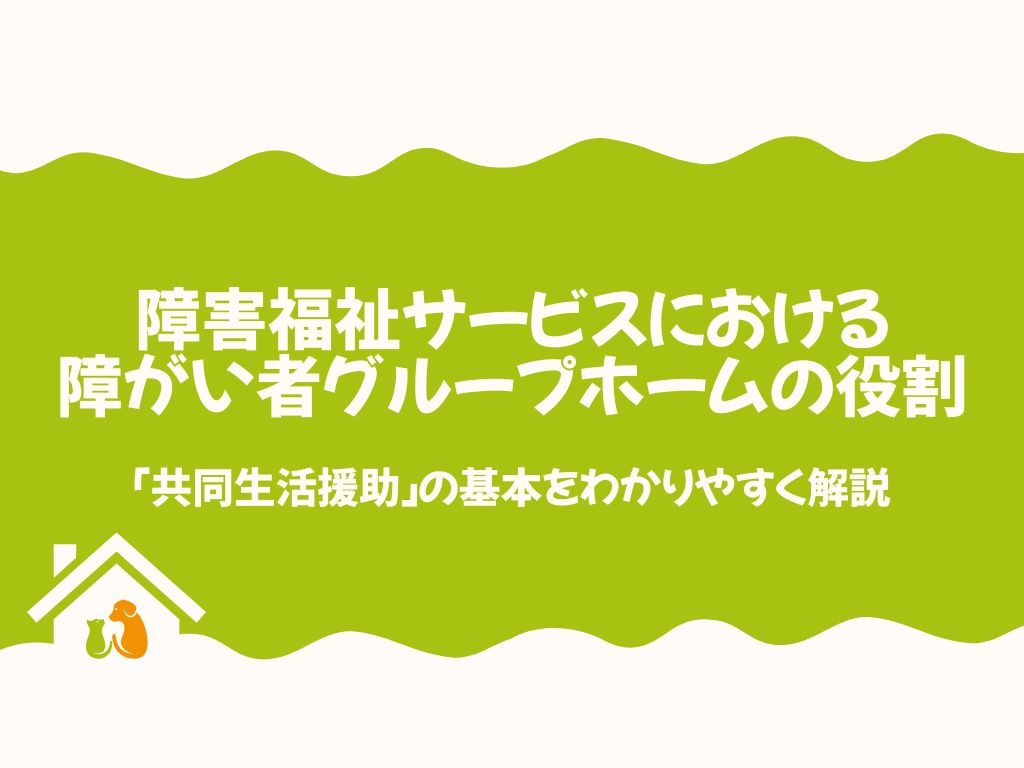
【はじめに】障がいのある方の「自分らしい暮らし」を支える選択肢
「いつかは親元を離れて自立したいけれど、一人暮らしは少し不安…」
「日中は作業所に通っている。でも、家に帰ると一人で、話し相手もいなくて寂しいな…」
「家族も高齢になってきて、この先の暮らしをどうしようか、親子で悩んでいる」
今、この記事を読んでくださっているあなたは、ご自身や大切なご家族の将来の暮らしについて、このような想いや悩みを抱えているのかもしれません。
障がいのある方が、住み慣れた地域で、安心して自分らしい生活を送る。そのための選択肢は、決して一つではありません。その中でも、近年注目を集めているのが、障がい者グループホームです。
この記事では、障害福祉サービスの一つである「障がい者グループホーム」について、その基本的な役割から、具体的なサービス内容、費用、利用までの流れまで、どこよりも分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「グループホームって、こんな場所だったんだ!」「自分(うちの子)にも合うかもしれない」と、漠然とした不安が具体的な希望に変わっているはずです。あなたの、そしてご家族の「自分らしい暮らし」への大切な一歩を、一緒に踏み出していきましょう。
1.障がい者グループホーム(共同生活援助)とは?
まず、「障がい者グループホーム」とは一体どのような場所なのでしょうか。その基本から見ていきましょう。
1-1.障害者総合支援法にもとづく「共同生活援助」という福祉サービス
「障がい者グループホーム」というのは一般的な呼び名で、法律上の正式名称は「共同生活援助」と言います。
これは、国が定めた「障害者総合支援法」という法律にもとづく、公式な障害福祉サービスの一つです。
「法律」や「サービス」と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、要は、国が認めた安心できる「住まいの形」であると理解してください。主にアパートやマンション、一戸建ての住居で、数人の障がいのある方々が、専門スタッフ(世話人や生活支援員)のサポートを受けながら共同で生活する場所です。
1-2.目的は「地域の中での自立した日常生活」の実現
障がい者グループホーム(共同生活援助)の最も大切な目的は、入居する一人ひとりが「地域社会の一員として、自立した日常生活を送ること」を支援することにあります。
単に寝泊まりする場所を提供するだけではありません。食事の準備や掃除といった家事、金銭管理、健康管理など、日々の暮らしで困ったことや苦手なことをスタッフがサポートし、入居者自身ができることを少しずつ増やしていく。そうして、自信を持って社会生活を送れるように後押しする「暮らしの拠点」であり、「自立への練習の場」なのです。
1-3.他の障害福祉サービスとの違い(入所施設や一人暮らしとの比較)
障がいのある方の住まいの選択肢として、グループホームの他に「入所施設(障害者支援施設)」や「一人暮らし」があります。それぞれの違いを理解することで、障がい者グループホームの特徴がより明確になります。
| 障がい者グループホーム(共同生活援助) | 入所施設(障害者支援施設) | 一人暮らし | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 地域での自立した生活 | 施設内での生活支援・介護 | 完全な自立 |
| 場所 | 地域の中にあるアパートや一戸建て | 比較的郊外にある大規模な施設が多い | 自由 |
| 生活スタイル | 少人数での共同生活。プライベートな個室あり | 大人数での集団生活 | 完全に個人 |
| 支援体制 | 夜間や休日も含め、生活全般をサポート | 24時間体制で手厚い介護・支援 | 基本的に全て自分で行う |
| 自由度 | 比較的高い(外出・外泊など) | 施設ごとの規則による | 非常に高い |
| キーワード | 地域移行・自立支援 | 生活介護・常時介護 | 完全自立 |
このように、障がい者グループホームは、手厚い支援が必要な「入所施設」と、全てのことを自分で行う「一人暮らし」の、ちょうど中間に位置する選択肢と言えます。支援を受けながらも、より地域に溶け込み、自由度の高い生活を送りたいと考える方に最適な障害福祉サービスなのです。
2.グループホームではどんなサービスを受けられる?
では、障がい者グループホーム(共同生活援助)では、具体的にどのようなサポートを受けられるのでしょうか。事業所によって特色はありますが、主に以下のようなサービスが提供されます。
2-1.日常生活のサポート(食事、入浴、掃除など)
毎日の生活に欠かせない、食事や入浴、居室の掃除などをサポートします。
食事の提供
栄養バランスの考えられた温かい食事が朝・夕に提供されるのが一般的です。スタッフと一緒に調理をしたり、自分でできる範囲の片付けをしたりすることで、生活能力の向上も目指します。
入浴の支援
一人で入浴するのが難しい方には、安全に入浴できるよう見守りや介助を行います。
清掃・洗濯
共有スペース(リビング、トイレ、お風呂など)の清掃はスタッフが行うことが多いですが、ご自身の部屋の掃除や洗濯は、本人の能力に合わせて一緒に行い、やり方を覚える支援をします。
2-2.金銭管理や服薬管理の支援
自立した生活を送る上で非常に重要な、お金と健康の管理についてもサポートします。
金銭管理
お給料や障害年金の管理が苦手な方に対して、お小遣い帳のつけ方を一緒に練習したり、計画的なお金の使い方ができるようアドバイスしたりします。財産を預かって管理するというよりは、ご本人が自分で管理できるようになるための「支援」が中心です。
服薬管理
薬の飲み忘れや飲み間違いがないよう、声かけや確認を行います。薬の整理を手伝ったり、定期的な通院に付き添ったりすることもあります。
2-3.健康管理と医療機関との連携
日々の健康状態をしっかり見守り、いざという時には迅速に対応できる体制が整っています。
日々の健康チェック: スタッフは毎日のコミュニケーションの中で、入居者さんの表情や言動から体調の変化を察知するよう努めています。定期的な検温や血圧測定を行うホームもあります。
医療機関との連携: かかりつけの病院や訪問看護ステーションと密に連携を取り、入居者一人ひとりの健康情報を共有しています。体調が急変した際には、速やかに医療機関に連絡し、適切な対応をとります。
2-4.日中活動の場(職場など)との連絡・調整
多くの入居者さんは、日中は職場や就労継続支援(A型・B型)、生活介護などの事業所に通っています。障がい者グループホームのスタッフは、それらの日中活動先と連絡を取り合い、本人の様子や課題を共有します。
例えば、「職場で少し疲れ気味のようだから、ホームではゆっくり休めるように配慮しよう」「最近、作業の集中力が続かないと相談があったから、睡眠時間を見直してみようか」といったように、生活の場と活動の場が一体となって、その人らしい安定した毎日を支えます。
2-5.緊急時の対応と夜間の支援体制
一人暮らしで最も不安なのが、夜間や緊急時の対応です。障がい者グループホームでは、その不安を解消するための体制が整っています。
夜間支援
夜間もスタッフが常駐またはオンコール(緊急時に駆けつけられる)体制をとっており、体調不良やトラブルが発生した際にもすぐに対応できます。夜中に不安な気持ちになった時に、話を聞いてくれるスタッフがいるだけでも、大きな安心に繋がります。
3.グループホームでの暮らしを具体的にイメージしてみよう
理屈は分かっても、実際の生活がどんなものか、なかなか想像しづらいかもしれません。ここでは、ある障がい者グループホームで暮らすAさんの1日を例に、暮らしの様子を覗いてみましょう。
3-1.ある入居者さんの1日のスケジュール例
| 時間 | Aさんの過ごし方 | スタッフのサポート |
|---|---|---|
| AM 6:30 | 起床。リビングへ行き、他の入居者さんと「おはよう!」と挨拶。 | スタッフが笑顔で出迎え、体調に変わりがないか優しく声かけ。 |
| AM 7:00 | 朝食。みんなでテレビを見ながら、和やかに食事。 | 栄養バランスの取れた朝食を提供。薬の飲み忘れがないか確認。 |
| AM 8:00 | 身支度。自分の部屋で着替えや準備をする。 | 「忘れ物はない?」「今日の天気は寒いから上着を持っていこうか」など、出発の準備を手伝う。 |
| AM 8:30 | 「いってきます!」と元気に出発。就労継続支援B型事業所へ。 | 「いってらっしゃい!気をつけてね」と笑顔で送り出す。 |
| (日中) | 事業所で軽作業やレクリエーションに参加。 | |
| PM 4:30 | 「ただいま!」とグループホームに帰宅。 | 「おかえりなさい!今日もお疲れ様」と出迎える。日中活動の様子などを聞く。 |
| PM 5:00 | 自由時間。自分の部屋で音楽を聴いたり、リビングで他の入居者さんとおしゃべりしたり。 | |
| PM 6:30 | 夕食。今日の出来事を話しながら、みんなで楽しく食べる。 | 温かい夕食を提供。希望者には晩酌(ルールあり)の準備も。 |
| PM 7:30 | 入浴。順番に気持ちよくお風呂に入る。 | 必要に応じて、洗髪や背中を流すなどの介助を行う。 |
| PM 8:00 | 自由時間。共有リビングのテレビで好きなドラマを見る。 | スタッフも一緒に見ながら、何気ない会話を楽しむ。悩み事の相談に乗ることも。 |
| PM 10:00 | 就寝。「おやすみなさい」と挨拶して自室へ。 | 各部屋を回り、就寝の確認。夜間も定期的に見守りを行う。 |
これはあくまで一例ですが、支援を受けながらも、自分のペースで、そして他の人との関わりの中で、温かい日常が流れていることを感じていただけたのではないでしょうか。
3-2.年間行事やイベントについて(季節の行事、外出レクなど)
多くの障がい者グループホームでは、日々の生活に彩りを加えるための年間行事やイベントを企画しています。
季節の行事
お花見、七夕、クリスマス会、餅つきなど、季節を感じられるイベント。
誕生日会
入居者さん一人ひとりの誕生日をみんなでお祝いします。
外出レクリエーション
みんなでバスに乗って少し遠出をしたり、近所のレストランに外食に行ったり。
地域のお祭りへの参加
地域の一員として、町内会のお祭りやイベントに参加することもあります。
こうした行事を通して、他の入居者さんやスタッフとの絆が深まり、楽しい思い出がたくさん作られていきます。
4.利用対象となるのはどんな方?
これほど手厚いサポートが受けられる障がい者グループホーム(共同生活援助)ですが、利用するためには一定の条件があります。
4-1.対象となる障がいの種類(身体・知的・精神・難病など)
基本的には、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)、そして国が定める難病などがある、18歳以上の方が対象となります。障がいの種類や程度は問いません。
ただし、グループホームによっては、「女性専用」「精神障がいのある方向け」など、対象者を限定している場合がありますので、事前に確認が必要です。
4-2.入居に必要な「障害支援区分」について
障がい者グループホームをはじめとする障害福祉サービスを利用するためには、「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
障害支援区分とは、その方がどのくらいの支援を必要とするかを客観的に示すための「ものさし」のようなものです。区分1から区分6まであり、数字が大きくなるほど、必要とされる支援の度合いが高いことを意味します。
この区分は、市区町村の職員などによる聞き取り調査(アセスメント)や医師の意見書などをもとに、専門家会議で審査・判定されます。共同生活援助の場合、原則として区分2以上の方が対象となりますが、自治体や個別の状況によっては区分1の方でも利用できる場合がありますので、まずは諦めずに相談することが大切です。
5.知っておきたいメリットと注意点
障がい者グループホームでの生活を検討するにあたり、良い面(メリット)と、事前に理解しておくべき注意点の両方を知っておくことは、後悔のない選択をするために非常に重要です。
メリット
①専門スタッフの支援のもと、安心して生活できる
何よりも大きなメリットは、困った時にいつでも相談できる専門スタッフがそばにいるという安心感です。体調のこと、お金のこと、人間関係の悩みなど、一人で抱え込まずに済みます。
②仲間との交流が生まれ、孤立を防ぐ
同じ屋根の下で暮らす仲間がいることは、大きな心の支えになります。一緒に食事をしたり、テレビを見たり、何気ない会話をしたりする中で、孤独感が和らぎ、社会性が育まれていきます。
③規則正しい生活習慣が身につく
食事や入浴の時間が決まっているため、自然と生活リズムが整います。一人暮らしだとつい昼夜逆転してしまったり、食事を抜いてしまったりしがちですが、グループホームでは健康的な毎日を送る習慣が身につきます。
④ご家族の身体的・精神的負担の軽減
ご本人の自立は、同時に、これまで支えてこられたご家族の負担を軽減することにも繋がります。「親なきあと」への不安が和らぎ、ご家族自身の時間やゆとりが生まれることも、非常に大きなメリットと言えるでしょう。
注意点
①共同生活ならではのルールがある
自分一人ではないため、共同生活を送る上でのルール(食事の時間、入浴の順番、共有スペースの使い方、門限など)が存在します。これは、みんなが気持ちよく、安全に暮らすために必要なものです。入居前に、どのようなルールがあるのかをしっかり確認し、自分が守れそうかを考えることが大切です。
②プライバシーの確保について
居室は個室でプライベートな空間が確保されていますが、リビングや食堂などは共有スペースとなります。完全に一人の時間を確保したい方にとっては、少し窮屈に感じる場面があるかもしれません。スタッフの出入りなどもあるため、一人暮らしと同じレベルのプライバシーを求めるのは難しい場合があります。
6.入居までの流れ【5ステップで解説】
「グループホームに興味が出てきた!」「一度、話を聞いてみたい」と思ったら、次はいよいよ具体的な行動に移す番です。ここでは、入居までの一般的な流れを5つのステップで解説します。
STEP1:相談(まずは市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所へ)
最初の第一歩は「相談」です。どこに相談すれば良いか分からない場合は、お住まいの市区町村の役所にある「障害福祉課(自治体によって名称は異なります)」の窓口を訪ねてみましょう。
そこで、「障がい者グループホーム(共同生活援助)を利用したい」と伝えれば、地域の相談窓口である「相談支援事業所」を紹介してくれます。
相談支援事業所には、「相談支援専門員」という、障害福祉サービスのプロがいます。あなたの希望や状況を丁寧にヒアリングし、あなたに合ったグループホームを探すお手伝いや、この後の手続きを全面的にサポートしてくれます。とても心強い味方なので、不安なことは何でも話してみてください。
STEP2:見学・情報収集
相談支援専門員と一緒に、いくつかの候補となる障がい者グループホームを見学に行きましょう。パンフレットやウェブサイトだけでは分からない、実際のホームの雰囲気や、スタッフ、他の入居者さんの様子を自分の目で確かめることが非常に重要です。
<見学時のチェックポイント>
- ホーム全体の雰囲気は明るいか?清潔か?
- スタッフの対応は丁寧で、入居者さんへの接し方はどうか?
- 他の入居者さんたちは、どのような表情で過ごしているか?
- 自分の部屋(個室)は、広さや設備など、希望に合っているか?
- 食事の内容や、共同生活のルールはどうか?
- 周辺の環境(駅からの距離、スーパーや病院など)はどうか?
STEP3:体験利用
気になるグループホームが見つかったら、「体験利用」をしてみましょう。実際に数日間宿泊してみて、ホームでの生活を体験します。
食事や入浴、他の入居者さんとのコミュニケーションなどを実際に経験することで、「ここならやっていけそうか」「自分に合っているか」を最終的に判断することができます。利用者と事業所の双方にとって、ミスマッチを防ぐための大切なステップです。
STEP4:利用申請
体験利用を経て、入居の意思が固まったら、正式な利用申請の手続きに入ります。
障害福祉サービスを利用するために必要な「障害福祉サービス受給者証」の申請または変更手続きを、相談支援専門員のサポートを受けながら市区町村の窓口で行います。この時に、前述した「障害支援区分」の認定も併せて行われることが一般的です。
STEP5:契約・入居開始
市区町村から受給者証が交付されたら、いよいよグループホームの事業者と利用契約を結びます。契約内容(サービス内容、費用、ルールなど)をしっかりと確認し、納得した上で署名・捺印をしましょう。
そして、入居日を決め、引っ越しの準備を進めます。いよいよ、新しい生活のスタートです!
7.気になる費用について
新しい生活を始めるにあたって、やはり費用のことは一番気になるところだと思います。ここでは、障がい者グループホームでかかる費用の内訳と、負担を軽減するための制度について解説します。
7-1.毎月かかる費用の内訳(家賃、食費、水道光熱費など)
グループホームで毎月かかる費用は、大きく分けて以下の3つです。
①家賃
住居の家賃です。アパートタイプか一戸建てか、立地などによって金額は異なります。
②食費
朝・夕の食材料費や調理費です。
③水道光熱費・日用品費
電気、ガス、水道代や、トイレットペーパーなどの共用で使う日用品の費用です。
これらの合計額が、毎月の自己負担額の目安となります。多くのグループホームでは、これらの費用を合計して、月額6万円~8万円程度に設定していることが多いようです。
※障害福祉サービスの利用料(ヘルパーさんの人件費などに相当する部分)については、9割を国と自治体が負担し、自己負担は1割となります。ただし、所得に応じた上限額が定められており、多くの方が0円(無料)または低い負担額で利用しています。
7-2.国や自治体からの家賃補助制度について
「家賃の支払いが大変そう…」と感じるかもしれませんが、ご安心ください。国には、グループホームの家賃負担を軽減するための補助制度があります。
「特定障害者特別給付費(補足給付)」という制度で、低所得の方を対象に、月額1万円を上限として家賃が補助されます。
つまり、家賃が4万円のホームであれば、自己負担は3万円になるということです。
さらに、自治体によっては、国とは別に独自の家賃補助制度を設けている場合があります。お住まいの市区町村の障害福祉窓口で確認してみましょう。
7-3.障害年金でまかなえる?費用の具体例
多くの方が、障害基礎年金(令和6年度では1級が月額約8.5万円、2級が月額約6.8万円)の範囲内で、これらの費用を支払いながら生活しています。
<費用シミュレーション例>
家賃:40,000円
国の家賃補助:-10,000円
食費:30,000円
水道光熱費・日用品費:15,000円
月額合計:75,000円
この場合、障害基礎年金2級(約6.8万円)だけでは少し足りませんが、日中活動の工賃などを合わせることで、十分に生活費をまかなうことが可能です。お金のやりくりについてもスタッフが相談に乗ってくれるので、安心してください。
8.よくあるご質問(Q&A)
ここでは、障がい者グループホームを検討している方からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 日中は必ず仕事をしないといけませんか?
A. 必ずしもそうではありません。多くの方が就労継続支援事業所や一般企業などで日中活動をされていますが、体調などの理由で日中もホームで過ごされる方もいらっしゃいます。ご本人の状況に合わせて、無理のない生活スタイルを一緒に考えていきますので、ご相談ください。
Q. 門限や外泊にルールはありますか?
A. はい、安全管理のため、門限を設けているホームがほとんどです。また、外泊(実家への帰省など)については、事前に届け出をすれば可能な場合が多いです。ルールはホームによって異なりますので、見学の際にご確認ください。
Q. 家族や友人を呼ぶことはできますか?
A. 他の入居者さんのプライバシーに配慮する必要があるため、リビングなどの共有スペースに自由に出入りすることは難しい場合が多いです。ただし、事前に相談すれば、ご自身の居室で面会できるなど、ホームごとのルールがありますので、確認してみましょう。
Q. 一人部屋はありますか?
A. はい、現在の障がい者グループホームは、プライバシー保護の観点から、居室はすべて個室であることが基本となっています。ゆっくりと一人の時間を過ごせる空間が確保されていますので、ご安心ください。
【まとめ】安心して地域で暮らし続けるために
ここまで、障害福祉サービスとしての障がい者グループホーム(共同生活援助)について、詳しく解説してきました。
グループホームは、ただ住むだけの場所ではありません。
専門スタッフの温かいサポートを受けながら、仲間との交流を楽しみ、日々の暮らしを通して少しずつ自信をつけていく。そして、地域社会の一員として、自分らしく、堂々と生きていくための「大切な拠点」です。
ご本人にとっても、ご家族にとっても、「自立」への一歩を踏み出すことは、勇気がいることだと思います。たくさんの期待とともに、同じくらいの不安があるかもしれません。
でも、どうか一人で、ご家族だけで抱え込まないでください。
私たちは、あなたのその一歩を、全力でサポートする準備ができています。
この記事を読んで、少しでも「話を聞いてみたい」「実際の場所を見てみたい」と感じていただけたなら、ぜひお気軽にご連絡ください。
千葉県で障がい者グループホームをお探しなら、私たち「千葉SMILEHOUSE」にご相談ください。
私たちは、まるで本当の家族のような、温かく家庭的な雰囲気を大切にしています。経験豊富なスタッフが、お一人おひとりの個性とペースに寄り添い、安心できる毎日と「できる喜び」を育むお手伝いをいたします。
見学はいつでも大歓迎です。あなたの不安が安心に変わる場所が、ここにあります。
未来への扉を、一緒に開けてみませんか?。
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
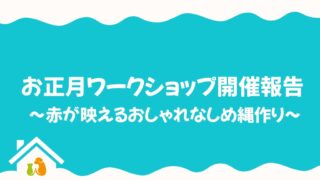 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告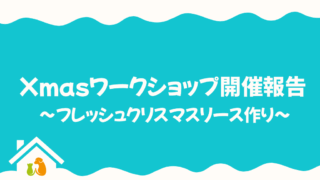 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告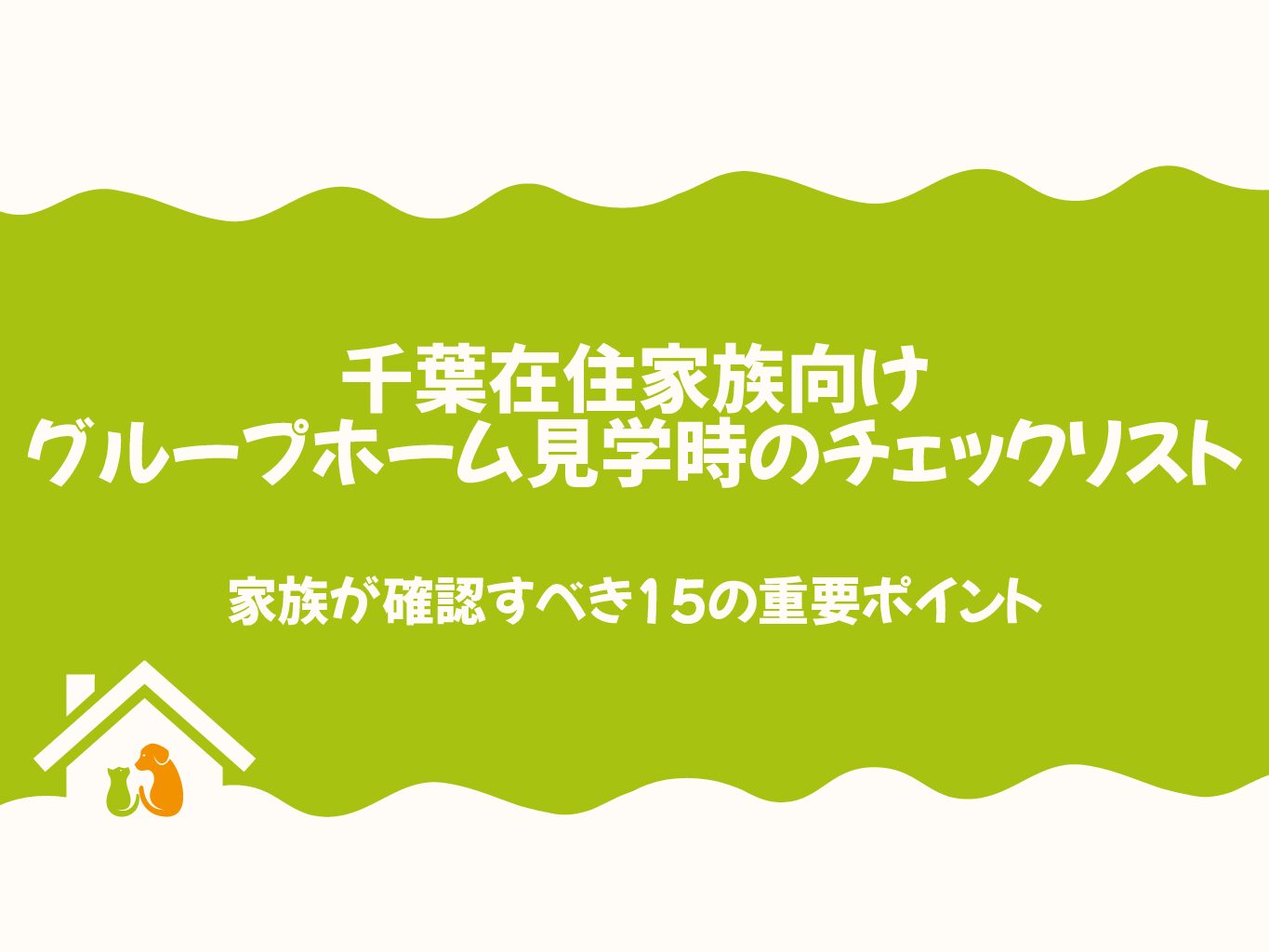 情報発信2025年11月27日千葉在住家族向け:グループホーム見学時のチェックリスト|家族が確認すべき15の重要ポイント
情報発信2025年11月27日千葉在住家族向け:グループホーム見学時のチェックリスト|家族が確認すべき15の重要ポイント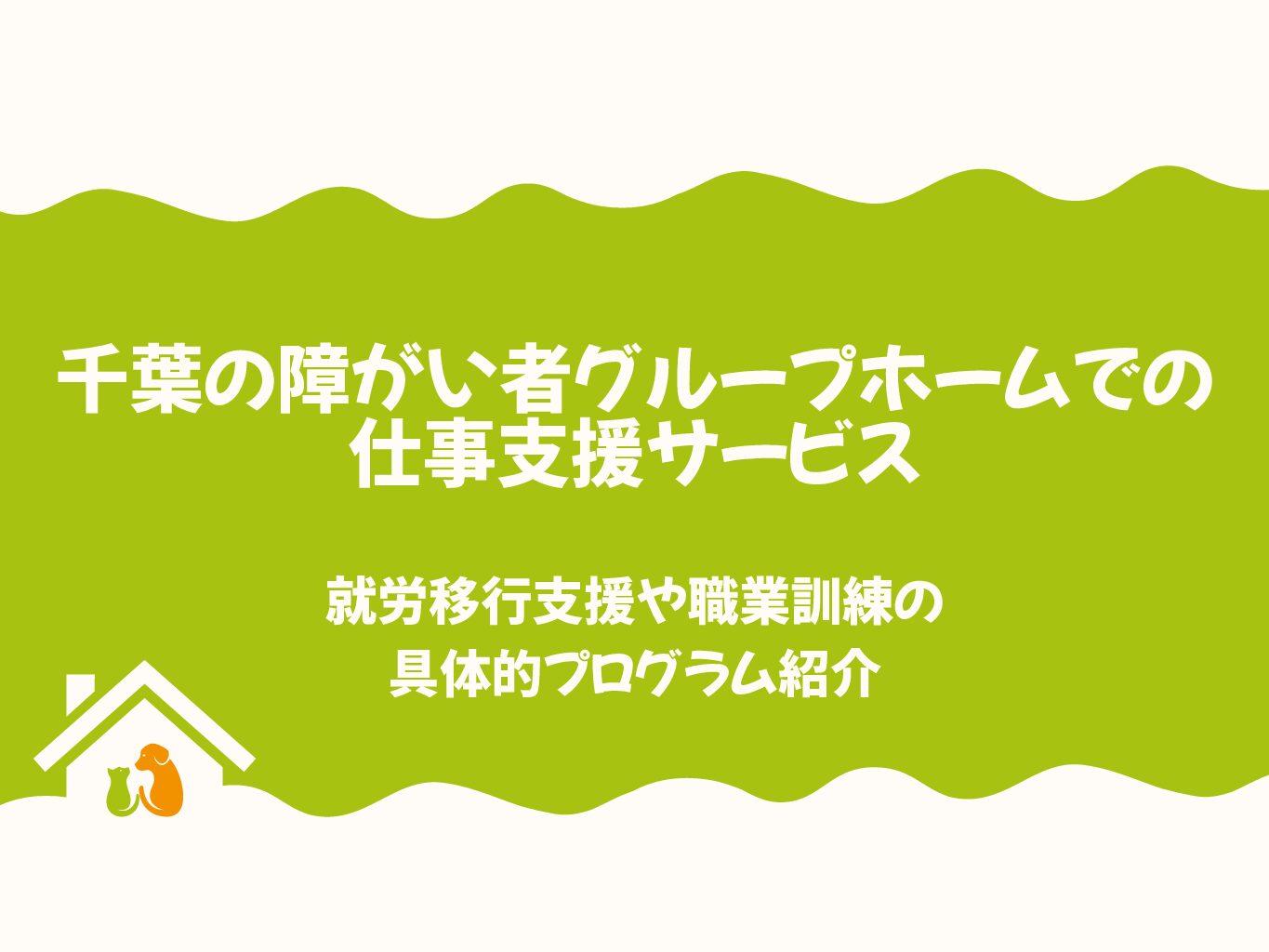 情報発信2025年11月20日千葉の障がい者グループホームでの仕事支援サービス|就労移行支援や職業訓練の具体的プログラム紹介
情報発信2025年11月20日千葉の障がい者グループホームでの仕事支援サービス|就労移行支援や職業訓練の具体的プログラム紹介