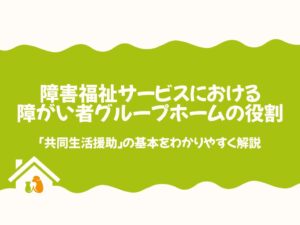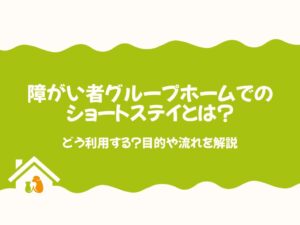千葉県にお住まいで、障がい者グループホームへの入居をご検討中の方、そしてそのご家族の皆様へ。
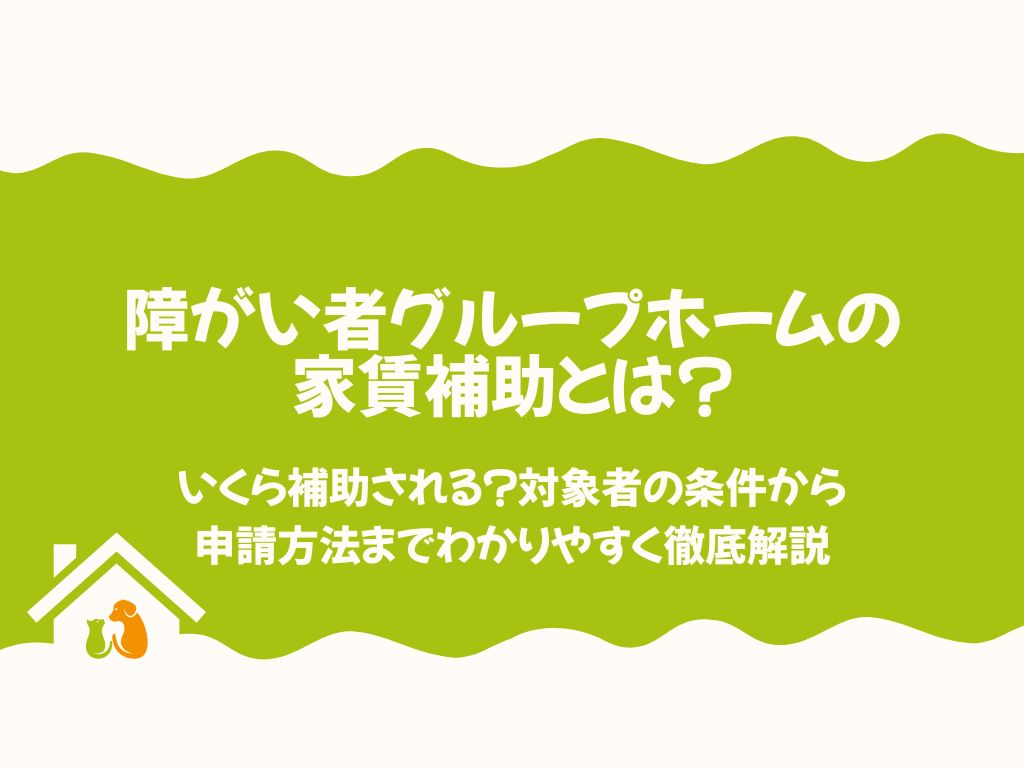
【はじめに】
「グループホームでの暮らしに興味はあるけれど、費用のことが心配…」
「家賃の負担を少しでも軽くする方法はないだろうか?」
新しい生活への期待とともに、こうした経済的な不安を抱えていらっしゃる方は少なくないでしょう。特に、毎月かかってくる家賃は、生活を送る上で大きな割合を占めるもの。
この負担が、グループホームという選択肢をためらわせる一因になっているかもしれません。
しかし、ご安心ください。
千葉県では、障がいのある方が地域で安心して暮らせるよう、国や県、そして市町村が連携して手厚い家賃補助制度を設けています。
これらの制度を正しく理解し、活用することで、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。
この記事では、障がい者グループホームの専門家として、千葉県で利用できる家賃補助制度の全貌を、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。国の制度から、千葉県独自の制度、さらには各市町村の助成金まで、あなたが利用できる可能性のあるすべての情報を網羅しました。
この記事を最後までお読みいただければ…
・どのような家賃補助制度があるのか
・自分は補助の対象になるのか
・具体的にいくら補助されるのか
・どのように申請すればよいのか
といった、あなたの疑問や不安がすべて解消されるはずです。
さあ、一緒に千葉県での安心な新生活への第一歩を踏み出しましょう!
1.千葉県の障がい者グループホーム家賃補助の概要
千葉県内で障がい者グループホームの利用を考えたとき、多くの方が直面するのが費用の問題です。
中でも家賃は毎月の固定費となるため、その負担は決して小さくありません。
しかし、千葉県では、国、県、市町村がそれぞれに家賃補助制度を設けており、これらを組み合わせることで負担を大きく減らすことが可能です。
この家賃補助制度は、大きく分けて以下の3つの階層で成り立っています。
①国の制度「特定障害者特別給付費(補足給付)」
全国の障がい者グループホーム利用者が対象となる基本的な家賃補助です。
②千葉県の制度「千葉県障害者グループホーム等支援事業」
国の制度に上乗せして、千葉県が独自に行う家賃補助です。
③市町村の制度
千葉市や船橋市、野田市など、各市町村が独自に設けているさらに手厚い家賃補助制度です。
重要なのは、「お住まいの市町村によって利用できる制度が異なる」という点です。
ご自身の状況と照らし合わせながら、どの制度が利用できるのかを正しく把握することが、家賃負担を最大限に軽減するための鍵となります。
この後の章で、それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
2. 障がい者グループホームとは?基本的な理解を深める
家賃補助の具体的な話に入る前に、まずは「障がい者グループホーム」そのものについて、基本的な理解を深めておきましょう。
2-1. 障がい者グループホームの基本概念
障がい者グループホーム(正式名称:共同生活援助)とは、障がいのある方々が、地域社会の中にあるアパートや一軒家で、少人数の仲間と共同生活を送るための住まいのことです。
専門のスタッフ(世話人や生活支援員)が常駐または巡回し、食事の準備や掃除、金銭管理、服薬、健康管理など、日常生活を送る上で必要なサポートを提供します。
単に生活の場を提供するだけでなく、日中の活動(仕事や作業所など)への送り出しや、休日の過ごし方についての相談に乗るなど、利用者が自立した生活を送りながら、地域社会とのつながりを築いていくことを目的としています。
ご家族の元を離れて自立したい、一人暮らしは不安だけれど日中は仕事に行きたい、という方々にとって、安心できる「我が家」のような存在です。
2-2. 千葉県内のグループホーム事情
千葉県は、都心へのアクセスも良く、自然も豊かな環境であることから、多くの障がい者グループホームが設置されています。
都市部から郊外まで、様々な地域に多様なタイプのグループホームが存在し、利用者一人ひとりのニーズに合わせた選択肢が比較的多いのが特徴です。
近年では、建物のバリアフリー化はもちろん、プライバシーに配慮した個室の整備や、日中の活動を支援するサービスが併設されたホームなど、より質の高い住環境を提供する事業所が増えています。
2-3. グループホームの種類とサービス内容
障がい者グループホームは、提供されるサービスの内容によって、主に以下の3つのタイプに分けられます。
①介護サービス包括型
主に夜間や早朝に、食事や入浴、排泄などの介護が必要な方向けのグループホームです。世話人に加えて生活支援員が配置され、手厚いサポートが受けられます。
②外部サービス利用型
夜間や休日は世話人によるサポートを受け、日中の介護や支援は外部の事業所(訪問介護など)を利用するタイプのグループホームです。ある程度、ご自身で生活ができる方向けです。
③日中サービス支援型
4時間を通じてスタッフが常駐し、日中もホーム内で生活相談や緊急時の対応、余暇活動の支援などを受けられるタイプです。障がいが重い方や、日中活動の場がない方でも安心して生活できます。
ご自身の心身の状態や、どのようなサポートを必要としているかに合わせて、最適なタイプのグループホームを選ぶことが大切です。
3. 【国制度】特定障害者特別給付費(補足給付)
まずご紹介するのが、全国共通の制度である「特定障害者特別給付費(補足給付)」です。
これは、障がい者グループホームの家賃補助制度の最も基本となる部分です。
3-1. 特定障害者特別給付費とは
特定障害者特別給付費は、所得の低い障がい者の方の居住費(家賃)の負担を軽減するために、国がその費用の一部を給付する制度です。
グループホームに入居すると、サービス利用料とは別に家賃が発生しますが、この家賃負担を軽くするために、国が直接補助をしてくれる、というイメージです。
3-2. 補助金額:月額最大1万円の詳細
補助される金額は、月額1万円が上限です。
例えば、家賃が3万円のグループホームに入居した場合、この制度を利用すると1万円が補助され、自己負担は2万円になります。
もし家賃が1万円未満のホームであれば、その家賃額が補助の上限となります。
3-3. 対象者の条件
この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす方です。
・障がい者グループホーム(共同生活援助)に入居していること
・世帯の所得が市町村民税非課税であること
「市町村民税非課税世帯」とは、ご本人様と配偶者(いらっしゃる場合)の所得が一定の基準以下である世帯を指します。
ご自身が非課税世帯に該当するかどうかは、お住まいの市町村の税務課や障害福祉課で確認することができます。
生活保護を受給されている方は、家賃相当額が生活扶助として支給されるため、この制度の対象外となります。
3-4. 申請方法と必要書類
申請は、お住まいの市町村の障害福祉課の窓口で行います。
申請には、一般的に以下の書類が必要となります。
・申請書(窓口で受け取ります)
・障害福祉サービス受給者証
・入居するグループホームの賃貸借契約書や家賃額がわかる書類
・所得を証明する書類(市町村民税非課税証明書など)
グループホームのスタッフが申請手続きをサポートしてくれる場合も多いので、入居が決まったらまずは相談してみましょう。
3-5. 支給の仕組みと流れ
申請が受理され、支給が決定すると、補助金(1万円)は市町村から利用者が入居しているグループホーム事業者に直接支払われます。
そのため、利用者は補助金が差し引かれた後の家賃(例:家賃3万円 - 補助1万円 = 2万円)をグループホームに支払う形になります。これを「代理受領方式」と呼びます。利用者自身が現金を受け取るわけではない、という点を覚えておきましょう。
4. 【千葉県制度】千葉県障害者グループホーム等支援事業
国の制度に加えて、千葉県が独自に実施しているのが「千葉県障害者グループホーム等支援事業」です。
これにより、千葉県民はさらに手厚い家賃補助を受けられる可能性があります。
4-1. 千葉県独自の家賃補助制度
この制度は、国の補足給付だけではまかないきれない家賃負担をさらに軽減し、障がいのある方が千葉県内でより安心して生活できるようにすることを目的としています。
国の制度に上乗せされる形で支給されるのが大きな特徴です。
4-2. 補助金額と計算方法
補助される金額は、以下の計算式で決まります。
(月額家賃 - 国の補足給付費1万円)÷ 2
ただし、この計算で算出された額には上限が設けられています。
補助上限額:月額20,000円
例えば、家賃が6万円のグループホームに入居した場合で考えてみましょう。
まず、国の制度で1万円が補助されます。残りの家賃負担は5万円です。
千葉県の制度では、この5万円の半額、つまり2万5千円が補助対象となりますが、上限が2万円のため、補助額は2万円となります。
結果として、国と県を合わせて合計3万円(国1万円+県2万円)の補助が受けられ、自己負担は3万円(6万円-3万円)となります。
もし、国の補足給付を受けていない場合(例えば、家賃が1万円未満など)は、家賃の半額が補助され、その上限は月額2万5千円となります。
4-3. 対象自治体(千葉市・船橋市・柏市を除く)
ここで非常に重要な注意点があります。
この千葉県独自の家賃補助制度は、県内すべての市町村で利用できるわけではありません。
千葉市、船橋市、柏市の3市は、県から権限が移譲されており(中核市)、県とは別に独自の家賃補助制度を設けています。
そのため、この3市にお住まいの方は、県の制度ではなく、それぞれの市の制度を利用することになります。
我孫子市も以前は対象外でしたが、現在は県の事業対象となっています。
ご自身のお住まいの市町村が県の制度の対象となるか、次の章で解説する市町村独自の制度を持っているか、必ず確認が必要です。
4-4. 申請手続きと注意点
申請手続きは、国の制度と同様に、市町村の障害福祉課が窓口となります。
多くの場合、国の制度の申請と同時に行うことができます。必要書類なども基本的には同じですが、詳しくは窓口で確認してください。
この制度も、補助金はグループホーム事業者に直接支払われる代理受領方式が一般的です。
5. 【市町村制度】千葉県内各市町村の独自補助制度
千葉県では、国、県の制度に加えて、さらに多くの市町村が独自の家賃補助制度を設けています。ここでは、代表的な市の制度をご紹介します。ご自身のお住まいの市に独自の制度がないか、必ずチェックしましょう。
5-1. 千葉市グループホーム家賃助成事業
千葉市にお住まいの方は、「千葉市グループホーム家賃助成事業」を利用できます。
対象者
千葉市から共同生活援助の支給決定を受けており、生活保護を受けていない方。
補助金額
市民税非課税世帯: 月額家賃から国の補足給付費(1万円)を引いた額。上限20,000円。市民税課税世帯: 月額家賃の1/2。上限20,000円。
特徴
市民税が課税されている世帯でも、家賃の半額(上限2万円)が補助されるのが大きな特徴です。所得要件が緩和されているため、より多くの方が利用できる可能性があります。
5-2. 船橋市の家賃補助制度
船橋市も、千葉県から権限の移譲を受けた中核市として、独自の家賃補助制度を実施しています。
制度の詳しい内容や補助金額、対象者については、市の障害福祉関連の窓口で直接確認する必要があります。
船橋市にお住まいの方は、まずは「船橋市役所 障害福祉課」にご相談ください。
5-3. 野田市の障がい者グループホーム等入居者家賃助成金
野田市では、「障がい者グループホーム等入居者家賃助成金」という名称で、手厚い補助を行っています。
対象者
市民税非課税世帯の方(生活保護受給者は除く)。
補助金額
家賃から国の補足給付費(1万円)を控除した額の1/2。上限20,000円。
特徴
千葉県の制度とほぼ同等の内容ですが、市が主体となって運営しているため、申請手続きなどが市内で完結します。申請は原則として半年ごとに行い、半年分をまとめて助成する形となります。
5-4. 八千代市・白井市等その他市町村の制度
上記で挙げた市以外にも、多くの市町村で独自の家賃補助制度が設けられています。
例えば白井市では、「障害者グループホーム等入居者家賃助成」として、国の補助を受ける場合は家賃から国の補助額を引いた額の1/2(上限2万円)、国の補助を受けない場合は家賃の1/2(上限2万5千円)が助成されます。これは千葉県の制度と同内容です。
このように、市町村によって制度の有無や名称、内容が異なります。
ご自身の住民票がある市町村のウェブサイトを確認したり、障害福祉課に問い合わせたりすることが非常に重要です。
5-5. 各制度の比較表
ここまでの内容を分かりやすく表にまとめました。ご自身がどの制度の対象になるかを確認する際にお役立てください。
| 制度の主体 | 制度の名称(例) | 主な対象者 | 補助金額(月額・上限) | 対象エリア |
|---|---|---|---|---|
| 国 | 特定障害者特別給付費 | 市民税非課税世帯 | 10,000円 | 全国 |
| 千葉県 | 千葉県障害者グループホーム等支援事業 | 市民税非課税世帯 | 家賃から国庫補助を引いた額の1/2(上限20,000円) | 千葉市・船橋市・柏市を除く県内市町村 |
| 千葉市 | 千葉市グループホーム家賃助成事業 | 市民税非課税・課税世帯 | 非課税:家賃-国庫補助(上限20,000円) 課税:家賃の1/2(上限20,000円) |
千葉市 |
| 野田市 | 障がい者グループホーム等入居者家賃助成金 | 市民税非課税世帯 | 家賃から国庫補助を引いた額の1/2(上限20,000円) | 野田市 |
| 白井市 | 障害者グループホーム等入居者家賃助成 | 市民税非課税世帯 | 家賃から国庫補助を引いた額の1/2(上限20,000円) | 白井市 |
6. 家賃補助の対象者条件を詳しく解説
ここまでで、千葉県には様々な家賃補助制度があることをご理解いただけたと思います。
ここでは、改めて「自分が対象になるのか?」を判断するための条件を、より詳しく見ていきましょう。
6-1. 障害者手帳の有無と種類
家賃補助を含む障害福祉サービスを利用するためには、原則として障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)の交付を受けていることが前提となります。
手帳の種類によって利用できるサービスが制限されることは基本的にありません。
6-2. 所得制限(市町村民税非課税世帯)
国の「特定障害者特別給付費」や、千葉県、多くの市町村の家賃補助制度では、「市町村民税非課税世帯」であることが主な要件となっています。
これは、申請者本人とその配偶者(いる場合)の前年の所得が、法律で定められた基準額以下であることを意味します。
扶養家族の有無などによって基準額は変わります。
ご自身の世帯が非課税に該当するかどうか不明な場合は、お住まいの市町村の障害福祉課や税務担当課に問い合わせれば確認できます。
(千葉市のように、課税世帯でも対象となる独自の制度を持つ自治体もあります。)
6-3. 年齢制限と例外規定
障がい者グループホームの利用や家賃補助に、直接的な年齢の上限や下限はありません。
ただし、障害者総合支援法に基づくサービスであるため、基本的には18歳以上(場合によっては15歳以上)の障がいのある方が対象となります。
65歳以上の方でも、特定の条件(65歳になる前に5年間障害福祉サービスの利用実績があるなど)を満たせば、介護保険ではなく障害福祉サービスとしてグループホームを利用し、家賃補助を受けられる場合があります。
6-4. グループホームの種類による違い
家賃補助の対象となるのは、障害者総合支援法に基づき、都道府県または中核市から「指定」を受けた共同生活援助(グループホーム)事業所です。
無認可の施設や、体験利用の場合は、原則として家賃補助の対象外となるため注意が必要です。
入居を検討しているグループホームが指定事業所であるかどうかは、見学時や契約前に必ず確認しましょう。
7. 申請方法と手続きの流れ
「自分も家賃補助を受けられそう!」と分かったら、次は具体的な申請手続きです。ここでは、一般的な申請の流れをステップごとに解説します。
7-1. 申請窓口の確認方法
家賃補助に関するすべての手続きの出発点となるのは、お住まいの(住民票のある)市町村の担当窓口です。通常は、「障害福祉課」「障がい者支援課」といった名称の部署が担当しています。
まずは電話で問い合わせるか、直接窓口を訪れて、「グループホームの家賃補助について相談したい」と伝えましょう。
7-2. 必要書類の準備
窓口で案内を受けたら、必要な書類を準備します。市町村によって若干の違いはありますが、一般的には以下のものが必要になることが多いです。
支給申請書
窓口で配布されるか、市町村のウェブサイトからダウンロードできます。
障害者手帳または障害福祉サービス受給者証
ご自身の受給者情報がわかるもの。
賃貸借契約書の写し
入居するグループホームと交わした契約書。家賃額が明記されている部分が必要です。
家賃の支払いを証明する書類
領収書の写しなど。
世帯の所得状況がわかる書類
市町村民税の課税(または非課税)証明書。マイナンバーを提示することで省略できる場合もあります。
本人名義の預金通帳の写し
償還払い(後払い)の場合に振込先として必要です。
スムーズに手続きを進めるためにも、事前にリストアップして漏れなく準備しましょう。
7-3. 申請時期とタイミング
申請は、グループホームへの入居が決まった後、または入居と同時に行うのが一般的です。
制度によっては、年度ごとに申請期間が定められている場合や、半期ごとに申請を受け付ける場合(例:野田市)もあります。補助は申請した月以降が対象となることが多いため、入居が決まったら速やかに手続きを始めることが大切です。
7-4. 審査期間と結果通知
提出された書類をもとに、市町村で審査が行われます。
所得要件などを満たしているかが確認され、支給が適切であるかが判断されます。
審査にかかる期間は自治体によって異なりますが、通常1ヶ月程度です。
審査が完了すると、自宅に「支給決定通知書」などの書類が届き、補助が受けられるようになります。
7-5. 代理申請の可能性
申請手続きは、ご本人だけでなく、ご家族や法定代理人、またグループホームのスタッフなどが代行して行うことも可能です。
手続きに不安がある場合や、ご自身で窓口に行くのが難しい場合は、入居先のグループホームの担当者(サービス管理責任者など)に相談してみましょう。
多くの場合、申請をサポートしてくれます。
8. 補助金額の具体的な計算例
制度の仕組みがわかっても、「結局、自分の場合はいくらになるの?」というのが一番気になるところだと思います。
ここでは、具体的な家賃額を想定して、自己負担額がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。(※いずれも市民税非課税世帯の場合を想定)
8-1. 国制度のみ利用の場合
このケースは、市町村に独自の家賃補助制度がない場合に該当します。
家賃: 50,000円
国の補助: -10,000円
自己負担額: 40,000円
8-2. 国制度+県制度併用の場合
千葉市・船橋市・柏市以外の市町村にお住まいの場合です。
家賃: 60,000円
国の補助: -10,000円
県の補助: (家賃60,000円 - 国の補助10,000円)÷ 2 = 25,000円 → 上限適用で -20,000円
合計補助額: 30,000円
自己負担額: 30,000円
8-3. 国制度+市町村制度併用の場合(千葉市の例)
千葉市にお住まいの場合でシミュレーションしてみましょう。
家賃: 55,000円
国の補助: -10,000円
千葉市の補助: (家賃55,000円 - 国の補助10,000円)= 45,000円 → 上限適用で -20,000円
合計補助額: 30,000円
自己負担額: 25,000円
8-4. 家賃額別シミュレーション
様々な家賃のケースで、自己負担額がどう変わるかを表にまとめました。
| 月額家賃 | 自己負担額(国のみ) | 自己負担額(国+県/市町村)※ |
|---|---|---|
| 40,000円 | 30,000円 | 20,000円 |
| 50,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 60,000円 | 50,000円 | 30,000円 |
| 70,000円 | 60,000円 | 40,000円 |
※県・市町村の補助上限を2万円とした場合の計算例です。
このように、制度を組み合わせることで、家賃負担が大きく軽減されることがお分かりいただけると思います。
9. よくある質問と注意点
最後に、家賃補助制度に関して多くの方が疑問に思う点や、知っておくべき注意点をQ&A形式でまとめました。
9-1. 体験利用時の補助適用
Q. グループホームに正式に入居する前の「体験利用」でも、家賃補助は使えますか?
A. いいえ、原則として体験利用期間中は家賃補助の対象外です。補助は、正式な利用契約を結び、住民票を移すなど、そのホームを生活の拠点としてから適用されるのが一般的です。
9-2. 他の補助制度との併用
Q. 家賃補助以外にも、生活費などを補助してくれる制度はありますか?
A. はい、あります。障害福祉サービスには、サービス利用料の自己負担上限額を定める制度や、食費・光熱水費などの実費負担を軽減する制度など、様々な支援があります。家賃補助はあくまで「家賃」に対するものですので、他の生活費に関する支援については、別途市町村の窓口でご相談ください。
9-3. 途中転居時の取り扱い
Q. グループホームを途中で引っ越した場合、手続きはどうなりますか?
A. 別のグループホームに転居した場合や、市町村をまたいで引っ越した場合は、改めて新しい住所地で申請手続きが必要になります。補助の内容も転居先の自治体の制度が適用されることになるため、注意が必要です。
9-4. 申請遅れによる影響
Q. 申請が遅れてしまった場合、遡って補助金をもらえますか?
A. 原則として、補助は申請が受理された月からが対象となり、遡っての支給は認められない場合がほとんどです。入居が決まったら、一日でも早く申請手続きを始めることをお勧めします。
9-5. 所得変更時の手続き
Q. 就職して収入が増えた場合、何か手続きは必要ですか?
A. はい、必ず市町村の窓口に届け出が必要です。収入が増えた結果、市民税が課税されるようになると、補助の対象外になったり、補助額が減額されたりする場合があります。報告を怠ると、後で補助金を返還しなければならなくなる可能性もあるため、正直に申告しましょう。
【まとめ】千葉県での家賃補助を最大限活用するために
ここまで、千葉県における障がい者グループホームの家賃補助制度について、詳しく解説してきました。最後に、制度を最大限に活用するためのポイントをまとめます。
10-1. 補助制度活用のポイント
3つの階層を理解する: 家賃補助は「国」「県」「市町村」の3階建て。まずは国の1万円補助が基本です。
自分の市町村を調べる: ご自身がお住まいの市町村が、県の制度の対象か、それとも独自の制度を持っているかを確認することが最も重要です。
所得要件を確認する: 多くの制度は「市民税非課税世帯」が対象です。ご自身の世帯の所得状況を把握しておきましょう。
とにかく窓口に相談する: 不明な点があれば、一人で悩まずに、必ずお住まいの市町村の障害福祉課に相談しましょう。専門の職員が、あなたの状況に合った最適な制度を教えてくれます。
10-2. 相談窓口と支援機関
家賃補助の申請やグループホーム探しで頼りになるのは、市町村の窓口だけではありません。
相談支援事業所: あなたのサービス等利用計画を作成してくれる相談支援専門員は、利用できる制度についても詳しい知識を持っています。
グループホームのスタッフ: 入居を検討している、あるいは入居中のグループホームのサービス管理責任者や世話人も、手続きの強力なサポーターです。
これらの専門家と連携を取りながら、手続きを進めていきましょう。
10-3. グループホーム選びのアドバイス
千葉県での障がい者グループホーム生活は、これらの手厚い家賃補助制度を活用することで、決して手の届かないものではありません。経済的な不安が解消されれば、ご本人もご家族も、より前向きに新しい一歩を踏み出すことができるはずです。
大切なのは、情報を知ることから始めること。
そして、勇気を出して専門家に相談してみることです。
私たち千葉SMILEHOUSEは、千葉県内で動物と暮らすことができる障がい者グループホームです。
この記事で解説したような家賃補助制度の活用はもちろん、入居に関するあらゆるご相談に応じています。
「もう少し詳しく話を聞いてみたい」
「うちの場合は、どれくらい補助が受けられるんだろう?」
「一度、ホームの雰囲気を見てみたい」
どんな些細なことでも構いません。
あなたの不安や疑問に、スタッフが親身になってお答えします。
見学は随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
あなたとご家族が、心から安心できる「新しい我が家」を見つけるお手伝いができれば幸いです。
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
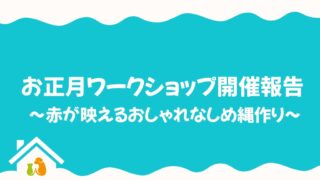 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告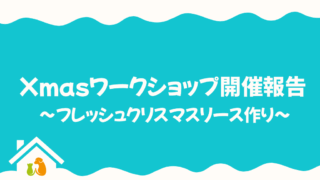 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告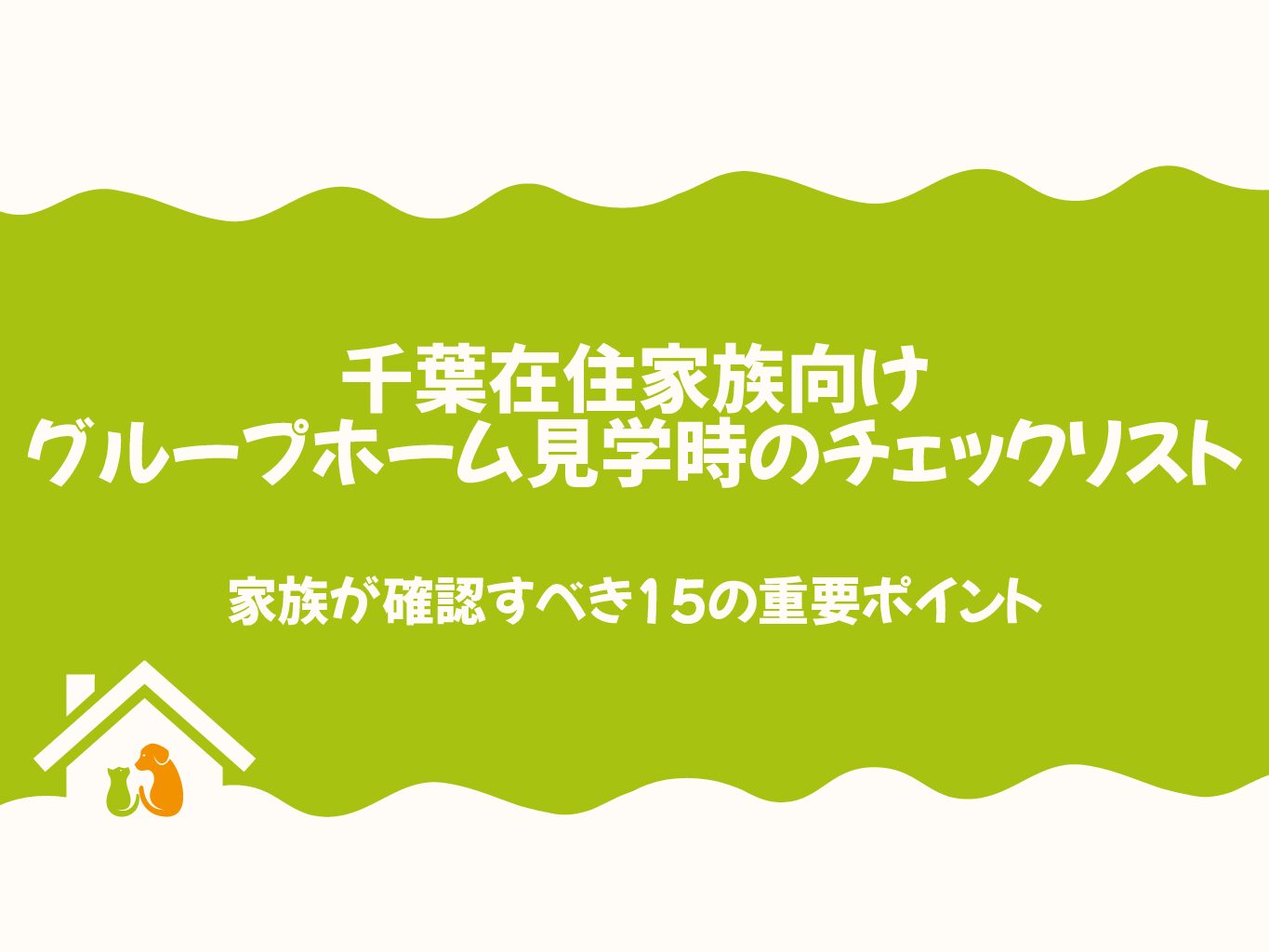 情報発信2025年11月27日千葉在住家族向け:グループホーム見学時のチェックリスト|家族が確認すべき15の重要ポイント
情報発信2025年11月27日千葉在住家族向け:グループホーム見学時のチェックリスト|家族が確認すべき15の重要ポイント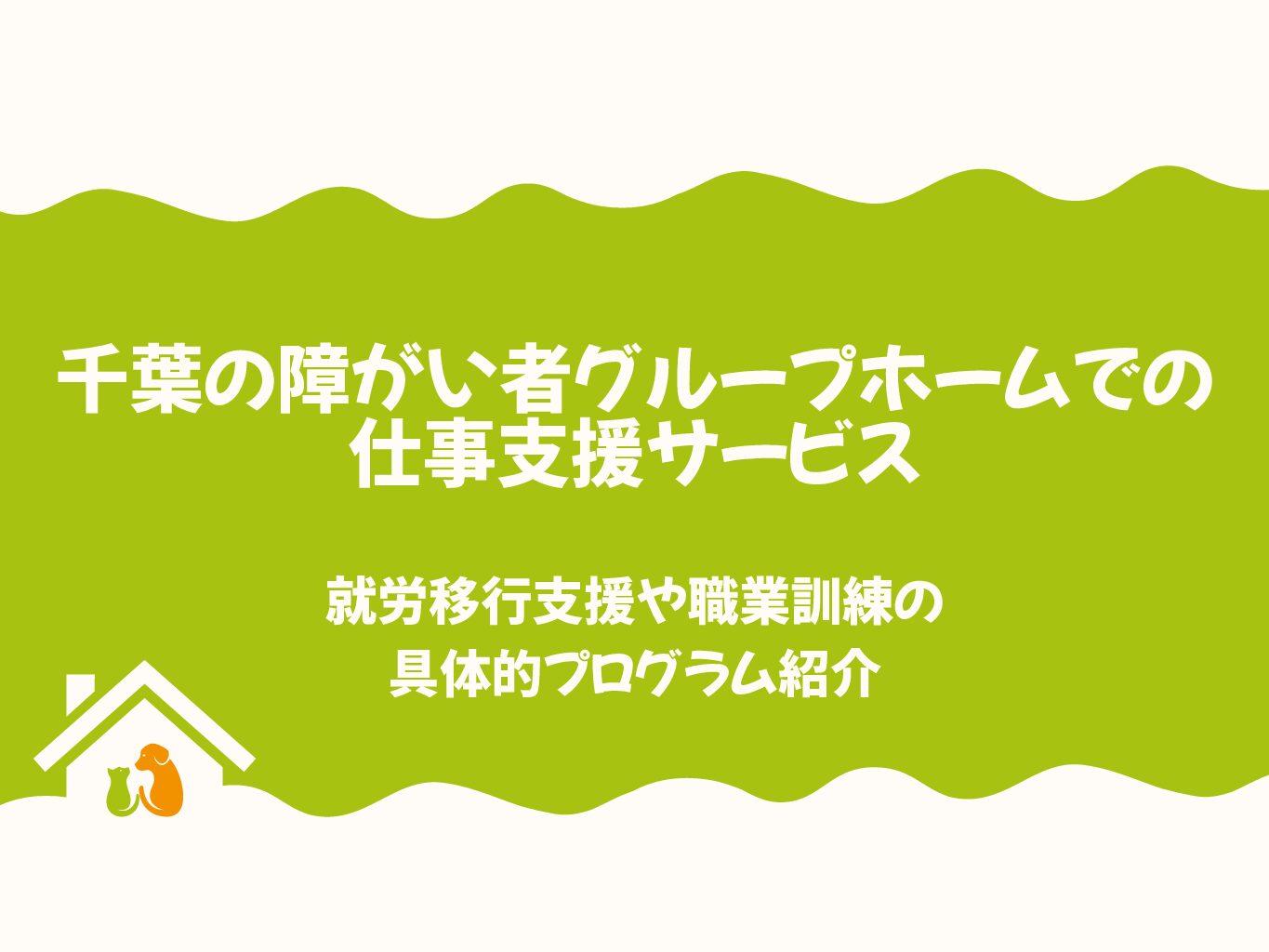 情報発信2025年11月20日千葉の障がい者グループホームでの仕事支援サービス|就労移行支援や職業訓練の具体的プログラム紹介
情報発信2025年11月20日千葉の障がい者グループホームでの仕事支援サービス|就労移行支援や職業訓練の具体的プログラム紹介