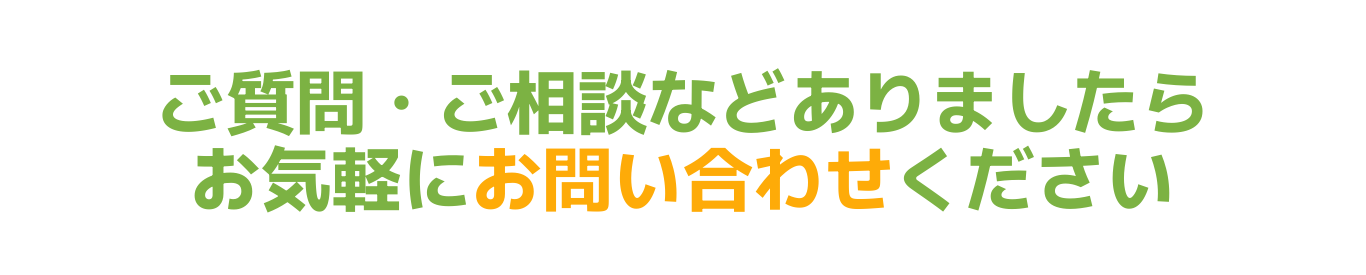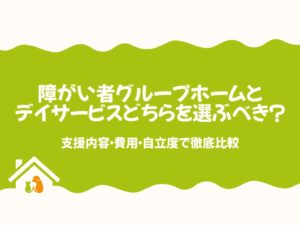障がい者グループホーム入居前に知っておきたい制度と申請方法|安心の支援を受けるための「障害福祉サービス」「住宅手当」「助成金」申請ガイド2025年版
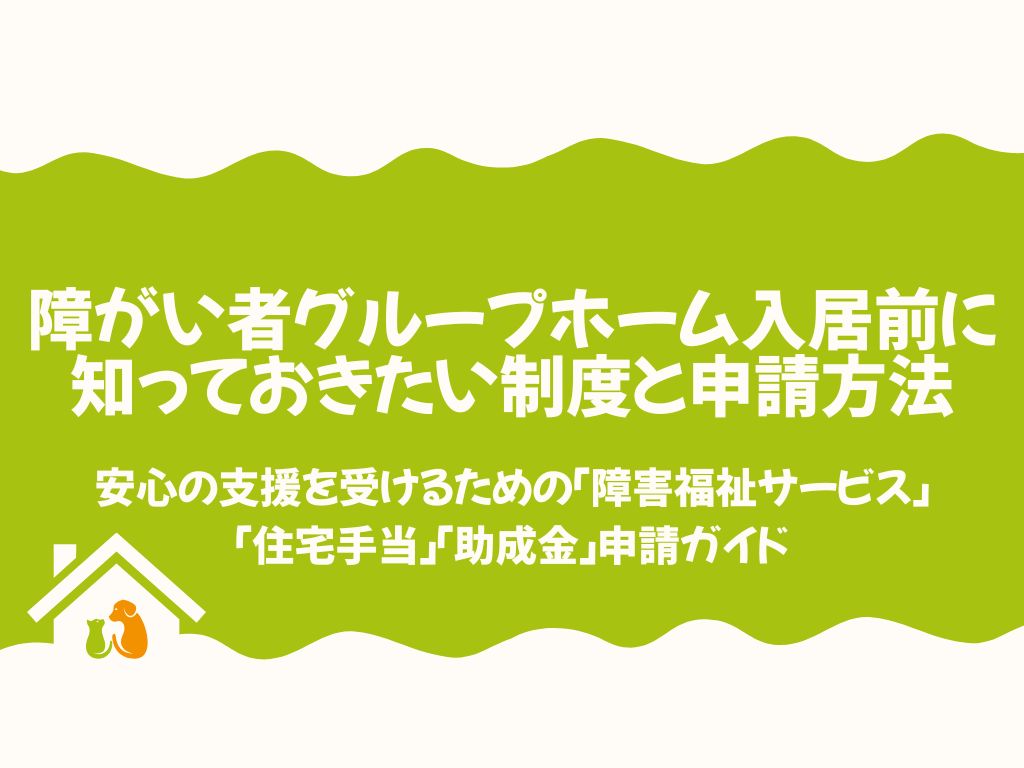
【はじめに】
「障がいを持つ家族が、安心して自立した生活を送れる場所はないだろうか…」
「グループホームに興味はあるけれど、手続きや費用が複雑で、何から手をつければいいのか分からない…」
このページを訪れたあなたは、ご自身や大切なご家族のために、障がい者グループホームという選択肢を考え、様々な期待と同時に、多くの不安や疑問を抱えているのではないでしょうか。
障がい者グループホームでの生活は、ご本人の自立を促し、地域社会とのつながりを育むための素晴らしい一歩です。
しかし、その一歩を踏み出すためには、「障害福祉サービス」の申請、家賃負担を軽減する「住宅手当」、そして様々な「助成金」といった、少し複雑に思える制度を理解し、適切に活用することが不可欠です。
この記事は、そんなあなたの羅針盤となることを目指して執筆しました。
2025年版の最新情報に基づき、専門用語をできる限り使わず、一つひとつのステップを丁寧に解説していきます。
この記事を最後まで読めば、あなたは以下のことができるようになります。
①複雑な制度の全体像をスッキリと理解できる
②入居までに何をすべきか、具体的な行動計画が立てられる
③費用に関する不安が解消され、経済的な見通しが立つ
④安心してグループホーム選びを始められる
大丈夫です、一人で悩む必要はありません。私たちと一緒に、安心できる未来への扉を開く準備を始めましょう。
1. 障がい者グループホームとは|基本概要と2025年の制度変更点
まずは「障がい者グループホーム」がどのような場所なのか、基本から確認していきましょう。
1-1.グループホームの基本的な概念と役割
障がい者グループホームは、正式には「共同生活援助」と呼ばれる障害福祉サービスの一つです。障がいのある方が、専門スタッフ(世話人や生活支援員)のサポートを受けながら、数人の仲間と一緒に共同で生活する住まいのことを指します。
単なる住居ではなく、以下のような重要な役割を担っています。
自立した日常生活の支援
食事の準備、掃除、金銭管理など、一人ひとりの状況に合わせて自立に向けたサポートを行います。
社会参加の促進
日中は職場や日中活動の場へ通い、帰ってきてから仲間と食卓を囲むといった、地域社会の一員としての生活を支えます。
安心できる居場所の提供
専門知識を持ったスタッフが常駐または巡回しているため、困ったことがあればすぐに相談でき、心身ともに安心して暮らせる環境が整っています。
1-2.2025年改正での制度変更の概要
福祉制度は、社会のニーズに合わせて常に変化しています。
2025年度もいくつかの制度改正が予定されており、グループホームのあり方にも影響を与えます。特に注目すべきは、利用者の多様なニーズに対応するための加算(事業所への報酬)が新設・拡充される点です。
重度障害者支援の強化
医療的ケアが必要な方や、行動障害が著しい方への支援体制を手厚く評価する動きが強まっています。
精神障害にも対応した個別の支援
精神障害を持つ方の地域移行や定着をより強力に支援するための仕組みが検討されています。
就労選択支援の導入
2025年10月から「就労選択支援」という新しいサービスが始まります。これは、グループホームに入居しながら、自分に合った働き方や仕事を見つけるためのサポートを受けられる制度です。
これらの変更は、より質の高い支援を受けられるようになるという点で、利用者にとって大きなメリットとなります。
1-3.誰が利用できるのか(入居対象者)
原則として、18歳以上(場合によっては15歳以上)の障がいのある方で、障害支援区分が認定されている方が対象となります。
・身体障害のある方
・知的障害のある方
・精神障害のある方
・発達障害のある方
・難病のある方
※ただし、「共同生活を送ることに支障がない」と判断される必要があります。具体的な入居条件はグループホームごとに異なるため、気になる施設があれば直接問い合わせてみましょう。
1-4.グループホーム利用のメリット
グループホームでの生活には、たくさんのメリットがあります。
自立へのステップアップ
親元を離れ、自分の力で生活するスキルを安全な環境で身につけることができます。
孤独感の解消
同じような境遇の仲間と支え合いながら生活することで、孤独や孤立を防ぎます。
家族の負担軽減
24時間体制の介護から解放されることで、ご家族も心身の休息を取ることができ、ご本人と良好な関係を築きやすくなります。
専門的なサポート
福祉の専門家から、健康管理や金銭管理、人間関係の悩みなど、幅広い相談に乗ってもらえます。
2. 入居前に必ず知っておきたい障害福祉サービスの基礎知識
グループホームを利用するためには、「障害福祉サービス」の利用申請が必須です。
ここでは、その根幹となる3つのキーワード「受給者証」「障害支援区分」「サービス等利用計画」について解説します。
2-1.障害福祉サービスとは何か
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づき、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を送れるように支援するための公的なサービス全般を指します。グループホーム(共同生活援助)も、この中の一つです。
他にも、日中の活動を支援する「生活介護」や「就労継続支援」など、様々な種類があります。
これらのサービスを利用するには、後述する「受給者証」が必要になります。
2-2.受給者証の仕組みと重要性
「障害福祉サービス受給者証」(または単に「受給者証」)は、市区町村から交付される「サービスの利用許可証」のようなものです。
この受給者証には…
・利用できるサービスの種類
・1ヶ月に利用できる日数や時間(支給量)
・利用者負担額の上限
…などが記載されています。
グループホームと契約する際には、この受給者証を提示する必要があります。
いわば、サービスを利用するための「パスポート」のような、非常に重要な書類です。
2-3.障害支援区分認定とその役割
「障害支援区分」とは、その人がどのくらいのサポートを必要とするかを示す「ものさし」です。
区分1から区分6までの6段階に分かれており、数字が大きいほど、より多くの支援が必要であることを意味します。
この区分は、医師の意見書や、市区町村の認定調査員によるご本人・ご家族への聞き取り調査(80項目にわたるアセスメント)などを基に、専門家が集まる審査会で総合的に判定されます。
グループホームに入居するには、原則として区分1以上の認定が必要となります。
2-4.サービス等利用計画の概要
「どの障害福祉サービスを、どのくらい、どのように利用するのがご本人にとって最適か」をまとめたものが「サービス等利用計画」です。
これは、指定特定相談支援事業所に所属する相談支援専門員が、ご本人やご家族の希望を聞きながら作成します。
この計画書があることで、グループホームの利用だけでなく、日中の活動(就労支援など)やその他のサービスを組み合わせて、一人ひとりの目標に合ったトータルな支援パッケージを作ることができます。市区町村は、この計画案を参考にして、最終的なサービスの支給量を決定します。
3. 障害福祉サービス申請の完全ガイド
では、実際に障害福祉サービスを申請するには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、申請から利用開始までの流れを4つのステップに分けて具体的に解説します。
3-1. 申請前の準備と相談窓口
すべては「相談」から始まります。
一人で抱え込まず、まずは専門家に話を聞いてもらいましょう。
市区町村の障害福祉担当窓口
最も身近な相談先です。お住まいの市役所や区役所の「障害福祉課」「福祉課」といった名称の部署が窓口になります。ここで、制度全体の流れや、お住まいの地域で利用できるサービスについての情報を得ることができます。
相談支援事業所
サービス等利用計画を作成してくれる専門機関です。どの事業所に相談すればよいか分からない場合は、市区町村の窓口で紹介してもらうことができます。相談支援専門員は、申請手続きのサポートから、あなたに合ったグループホーム探しまで、心強い味方となってくれます。
3-2. 申請に必要な書類と手続きの流れ
相談して方向性が見えたら、いよいよ申請手続きです。一般的に、以下の書類が必要となります。
①支給申請書
市区町村の窓口で受け取るか、ウェブサイトからダウンロードできます。
②障害者手帳
身体障害者手帳、療育手帳(愛の手帳)、精神障害者保健福祉手帳など。
③マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカードや通知カードなど。
④医師の意見書
精神科に通院している場合など、求められることがあります。
⑤世帯の所得が分かる書類
課税証明書など。利用者負担額を算定するために必要です。
これらの書類を揃えて、市区町村の窓口に提出します。自治体によっては郵送や電子申請に対応している場合もあります。
3-3. 障害支援区分認定調査
申請が受理されると、市区町村の認定調査員がご自宅や入所施設などを訪問し、心身の状況について聞き取り調査を行います。
調査内容
日常生活の動作、コミュニケーション能力、行動障害の有無など、80項目にわたる質問が行われます。
準備のポイント
ありのままの普段の様子を伝えることが大切です。
緊張して「できます」と答えてしまうと、実態よりも軽い区分になってしまう可能性があります。
事前にご家族や支援者と「困っていること」「サポートが必要なこと」をリストアップしておくと、伝え漏れが防げます。
この調査結果と医師の意見書を基に、前述の「障害支援区分」が決定されます。
3-4. 支給決定から受給者証交付まで
障害支援区分が決定し、サービス等利用計画案が提出されると、市区町村はそれらの内容を総合的に勘案して、支給内容を決定します。
決定内容に問題がなければ、いよいよ「障害福祉サービス受給者証」が自宅に郵送されます。この受給者証が手元に届いたら、晴れてグループホームと利用契約を結ぶことができるようになります。申請から受給者証の交付までは、一般的に1〜2ヶ月程度かかると考えておくとよいでしょう。
4. 住宅手当・家賃補助制度の詳細解説
グループホームの費用の中で、大きな割合を占めるのが「家賃」です。
しかし、ご安心ください。この負担を軽減するための住宅手当や家賃補助の制度が用意されています。
4-1. 国の制度:特定障害者特別給付費(補足給付)
これは、国が設けている家賃補助制度で、通称「補足給付」と呼ばれています。所得の低い方を対象に、グループホームの家賃の一部を補助するものです。
支給対象者
市町村民税が非課税の世帯に属する方。
支給額
家賃額に応じて、月額最大10,000円が支給されます。例えば、家賃が30,000円の場合、10,000円が補助され、自己負担は20,000円となります。
申請方法
障害福祉サービスの申請と同時に、市区町村の窓口で行うのが一般的です。専用の申請書に必要事項を記入して提出します。
この制度は、グループホーム利用者の多くが活用している基本的な家賃補助制度です。
4-2. 自治体独自の家賃補助制度
国の制度に加えて、多くの自治体が独自の家賃補助制度(住宅手当)を設けています。
制度の例
国の補足給付(10,000円)に、さらに上乗せで補助を行う制度。
国の制度の対象とならない方(市町村民税課税世帯)を対象とする制度。
補助額が国の制度より高額な制度。
⚠注意点: 制度の有無、対象者、補助額、申請方法は自治体によって大きく異なります。例えば、東京都の一部の区では、独自の住宅手当として手厚い補助が用意されている場合があります。
入居を検討しているグループホームがある市区町村のウェブサイトを確認したり、障害福祉担当窓口に直接問い合わせたりして、利用できる制度がないか必ず確認しましょう。
4-3. 申請から支給までの具体的な手順
家賃補助の申請も、基本的には障害福祉サービスの申請と並行して行います。
STEP①制度の確認
お住まいの市区町村に、国の制度以外に独自の家賃補助があるかを確認します。
STEP②書類の準備
申請書、所得証明書、賃貸借契約書の写しなど、指定された書類を準備します。
STEP③申請
市区町村の障害福祉担当窓口に書類を提出します。
STEP④審査・決定
提出された書類を基に審査が行われ、支給が決定します。
STEP⑤支給
支給方法は自治体によって異なります。利用者に直接振り込まれる場合もあれば、グループホーム事業者に直接支払われる(代理受領)場合もあります。
これらの制度を賢く活用することで、月々の家賃負担を大幅に軽減することが可能です。
5. 利用可能な助成金制度の総合ガイド
家賃だけでなく、生活費やその他の費用をサポートしてくれる助成金制度も存在します。ここでは、知っておくと役立つ代表的な制度をご紹介します。
5-1. 入居者向け助成金
障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金です。グループホームの利用料や生活費の大きな支えとなります。
生活保護
障害年金や就労による収入だけでは最低限度の生活を営むことが困難な場合に、不足分を補う形で支給されます。
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給される手当です。
自立支援医療制度
精神疾患や特定の身体障害の治療にかかる医療費の自己負担額を、原則1割に軽減する制度です。
5-2. 事業者向け補助金(間接的に利用者が恩恵を受けるもの)
直接お金を受け取るわけではありませんが、事業者が補助金を受けることで、結果的に利用者の生活の質が向上する制度もあります。
社会福祉施設等施設整備費補助金
グループホームの建設や改修、防災対策などにかかる費用を国や自治体が補助する制度です。これにより、安全で快適な住環境が整備されます。
職員処遇改善加算
職員の給与をアップさせるための加算です。職員の定着率が上がり、専門性の高い、安定した支援を受けられることにつながります。
地域生活支援拠点機能強化事業
緊急時の受け入れや相談対応など、地域全体のセーフティネット機能を担う事業所への補助です。こうした機能を持つグループホームは、いざという時の安心感が違います。
5-3. 地域独自の助成金制度
自治体によっては、さらに独自の助成金制度を設けている場合があります。
・入居一時金の補助
・退去後のアパート契約費用の補助
・日用品購入費の助成
など、内容は様々です。これらも住宅手当と同様に、お住まいの市区町村の窓口で確認することが重要です。諦めずに情報を集めることが、経済的な負担を軽くする鍵となります。
6. グループホーム入居までの実践的な手続きマニュアル
制度の知識が身についたら、次は実践です。実際にグループホームを見つけ、入居するまでの具体的なステップを見ていきましょう。
6-1. 入居検討から申し込みまで
施設見学のポイント: パンフレットやウェブサイトだけでは分からない、施設の「空気感」を知ることが最も重要です。
雰囲気
スタッフと利用者の表情は明るいか、楽しそうに会話しているか。
清潔感
居室や共有スペースは清潔に保たれているか。
支援内容
自分の希望する支援(金銭管理、服薬管理など)が受けられるか具体的に質問する。
体験入居の活用
多くのグループホームでは、数日間〜1週間程度の体験入居が可能です。実際の生活を体験することで、自分に合うかどうかを最終判断できます。食事は美味しいか、夜は静かに眠れるか、他の入居者と上手くやっていけそうかなど、五感で確かめましょう。
複数施設の比較検討
1ヶ所だけでなく、必ず2〜3ヶ所のグループホームを見学・体験することをおすすめします。比較することで、それぞれの長所・短所が見えてきて、自分にとっての「譲れない条件」が明確になります。
6-2. 契約手続きと重要事項説明
入居したいグループホームが決まったら、契約手続きに進みます。
契約書の確認ポイント
利用料金、サービス内容、禁止事項、退去に関する条件など、隅々まで目を通し、分からない点は必ず質問しましょう。
重要事項説明書の読み方
事業所の運営方針、職員の体制、苦情解決の仕組みなど、重要な情報が記載されています。特に、緊急時の対応方法や連携している医療機関については、しっかりと確認しておきましょう。
6-3. 入居準備と必要な持ち物
いよいよ入居です。慌てないように、事前に準備を進めましょう。
必要な書類
障害福祉サービス受給者証、障害者手帳、健康保険証、印鑑など。
生活用品
衣類: 日常着、パジャマ、下着、外出用の服など、季節に合わせて十分な量を。
洗面用具: 歯ブラシ、シャンプー、タオルなど。
その他
普段飲んでいる薬、個人の趣味の物(本、音楽プレイヤーなど)、使い慣れた寝具や小さな家具(持ち込み可能な場合)。
施設によって備え付けの物や持ち込める物が異なるため、事前にリストをもらって確認するとスムーズです。
7. 費用・料金体系の完全理解
お金のことは、最も気になる点の一つだと思います。ここでは、グループホームにかかる費用の内訳と、負担を軽減する仕組みについて詳しく見ていきます。
7-1. 利用料金の仕組み
グループホームの月額費用は、大きく分けて以下の3つで構成されます。
①障害福祉サービス費の自己負担額
サービス費全体の原則1割を負担しますが、所得に応じて月ごとの上限額が決められています。
生活保護・市町村民税非課税世帯: 0円
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満): 9,300円
上記以外(所得割16万円以上): 37,200円
多くの方は、負担上限月額が0円または9,300円に該当します。
②家賃
施設の立地や設備によって異なりますが、都市部でなければ3万円〜5万円程度が相場です。
この家賃から、前述の住宅手当(家賃補助)が差し引かれます。
③食費・水道光熱費・日用品費などの実費
食費は3万円前後、水道光熱費は1〜2万円程度が一般的です。これらは実際に利用した分を支払います。
7-2. 補助制度活用後の実際の負担額
では、制度を活用した場合、実際の負担額はどのくらいになるのでしょうか。モデルケースを見てみましょう。
【モデルケース】
障害支援区分3、市町村民税非課税世帯の方
グループホームの家賃:40,000円
食費・水道光熱費など:50,000円
| 項目 | 補助適用前 | 補助制度 | 補助適用後 |
|---|---|---|---|
| サービス自己負担 | 9,300円相当 | 所得区分による減免 | 0円 |
| 家賃 | 40,000円 | 国の家賃補助(補足給付) | 30,000円 |
| 食費・実費等 | 50,000円 | (対象外) | 50,000円 |
| 合計 | 99,300円 | 80,000円 |
※このケースでは、さらに自治体独自の家賃補助(住宅手当)が適用されれば、負担はさらに軽くなります。
※障害年金などの収入から、これらの費用を支払う形になります。
このように、障害福祉サービスの負担軽減措置や住宅手当を組み合わせることで、月々の負担を大きく抑えることが可能です。
8. 申請時の注意点とよくある質問
手続きを進める中で、誰もが一度はつまずきがちなポイントや疑問があります。
ここでは、それらを先回りして解説します。
8-1. 申請でよくある失敗とその対策
失敗例1:障害支援区分の認定調査で、普段より頑張って「できる」と答えてしまった。
対策: 調査はテストではありません。ありのままを伝えることが、適切な支援につながります。「いつもはできるけど、調子が悪いとできない」「手伝ってもらえればできる」など、具体的な状況を伝えることが重要です。事前に困りごとリストを作成し、調査員に渡すのも有効です。
失敗例2:どのグループホームがいいか分からず、情報収集だけで疲れてしまった。
対策: 100点満点の施設を探そうとすると、決断できなくなってしまいます。「これだけは譲れない」という条件を2〜3個に絞り、それに合う施設から見学を始めましょう。相談支援専門員に希望を伝え、候補を絞ってもらうのも良い方法です。
失敗例3:申請書類の不備で、手続きが大幅に遅れてしまった。
対策: 提出前に、市区町村の窓口担当者や相談支援専門員にダブルチェックをしてもらいましょう。特に、マイナンバーや所得証明など、他の家族の協力が必要な書類は早めに準備を依頼しておくことが大切です。
8-2. 制度変更への対応方法
2025年の制度改正のように、福祉制度は常に変化します。最新の情報を得ることが、最適なサービス選択につながります。
相談支援専門員との連携
担当の相談支援専門員は、制度改正のプロです。定期的に連絡を取り、最新情報を教えてもらいましょう。
市区町村からの広報を確認
自治体の広報誌やウェブサイトには、住民に関連する重要な制度変更が掲載されます。定期的にチェックする習慣をつけましょう。
8-3. FAQ(よくある質問と回答)
Q1. 障害者手帳がないと、グループホームには入れませんか?
A1. 自治体によっては、手帳がなくても医師の診断書や意見書があれば障害福祉サービスの申請が可能な場合があります。まずはお住まいの市区町村の窓口に相談してみてください。
Q2. 入居に年齢制限はありますか?
A2. 原則として18歳以上(知的障害のある方などは15歳以上)ですが、65歳以上の方は介護保険サービスが優先される場合があります。ただし、障がいの特性などにより、65歳以上でも入居できるケースは多くありますので、諦めずにご相談ください。
Q3. 働いていてもグループホームに入れますか?収入があると利用料は高くなりますか?
A3. もちろん入れます。多くの方が日中は就労しています。利用料のうち、障害福祉サービスの自己負担額は、前年の所得(収入から経費を引いた額)によって決まります。ただし、上限額が定められているため、収入が一定以上増えても負担が青天井に上がることはありません。
9. 入居後の継続的な支援とアフターフォロー
グループホームへの入居はゴールではなく、新しい生活のスタートです。入居後も、様々な支援を受けながら安心して生活を続けることができます。
9-1. 定期的な見直しとモニタリング
サービス等利用計画の見直し
相談支援専門員が定期的に(通常は半年に1回程度)グループホームを訪問し、ご本人の生活状況や意向を確認します。これを「モニタリング」と呼びます。この場で、「もっとこういう支援がほしい」「日中の活動内容を変えたい」といった希望を伝え、必要に応じて計画を見直していきます。
障害支援区分の更新
障害支援区分には有効期間があります。期間が終了する前に更新手続きが必要です。心身の状態に変化があった場合は、更新時期を待たずに区分の変更申請を行うことも可能です。
9-2. 相談支援の継続利用
入居後も、困ったことがあればいつでも相談支援専門員に連絡できます。グループホームのスタッフには直接言いにくい悩みや、将来の生活に関する相談など、第三者の立場から客観的なアドバイスをもらうことができます。
9-3. 自立に向けた支援制度
グループホームでの生活を経て、さらに自立度が高まった方には、一人暮らし(アパートなど)へ移行するための支援制度も用意されています。
自立生活援助
一人暮らしを開始した方のご自宅を支援員が定期的に訪問し、様々な相談に乗ったり、関係機関との連絡調整を手伝ったりしてくれるサービスです。
地域定着支援
一人暮らしで緊急の事態が起きた際に、すぐに相談できたり、駆けつけてくれたりする体制を整えるサービスです。
グループホームは、将来の完全な自立に向けた「練習の場」であり、「中継地点」としての役割も担っているのです。
10. 2025年版最新情報|制度改正と今後の展望
最後に、2025年の制度改正のポイントと、今後の動向について改めて整理します。
10-1. 2025年改正の主要ポイント
2025年度の報酬改定では、より手厚い支援や多様なニーズへの対応が評価される方向性が示されています。
自立生活支援加算の新設: グループホームから一人暮らしへ移行した利用者がいた場合に、事業所を評価する新しい加算です。これにより、事業所が利用者の「自立」をより積極的に後押しするインセンティブが働きます。
重度障害者支援加算の拡充: 医療的ケアが必要な方や強度行動障害のある方への支援体制を強化した事業所への評価が手厚くなります。これにより、これまで受け入れが難しかった重度の方の入居機会が増えることが期待されます。
地域居住支援体制強化推進加算: 地域移行や地域生活の継続を支援する役割を担う事業所への加算です。グループホームが単なる「住まい」だけでなく、地域の福祉拠点としての役割を果たすことが求められます。
10-2. 電子申請システムの導入状況
近年、行政手続きのデジタル化が進んでいます。障害福祉サービスの申請も、マイナポータルなどを活用した電子申請に対応する自治体が増えてきています。
メリット: 24時間いつでも申請可能、窓口に行く手間が省ける、書類の郵送代がかからない、など。
注意点: 現状ではすべての自治体・すべての手続きが対応しているわけではありません。また、パソコンやスマートフォンの操作に慣れていない方には、依然として窓口での対面サポートが重要です。
お住まいの自治体の対応状況を確認し、ご自身に合った方法で申請を進めましょう。
【まとめ】
安心してグループホーム生活を始めるために
ここまで、障がい者グループホームへの入居に向けて、障害福祉サービスの申請方法、住宅手当や助成金といった経済的支援制度、そして具体的な手続きの流れまで、詳しく解説してきました。
たくさんの情報があり、少し圧倒されてしまったかもしれません。しかし、最も大切なポイントは以下の3つです。
一人で抱え込まない: まずは市区町村の窓口や相談支援事業所など、専門家に相談することから始めましょう。彼らはあなたの最も心強い味方です。
制度を最大限活用する: 国や自治体には、あなたの負担を軽くするための様々な制度が用意されています。「知らなかった」で損をしないよう、積極的に情報を集め、活用しましょう。
ご本人の気持ちを尊重する: どんなに素晴らしい施設でも、ご本人が「ここで暮らしたい」と思えなければ意味がありません。見学や体験入居を通して、ご本人の意思を何よりも大切にしてください。
新しい環境への一歩は、誰にとっても勇気がいるものです。しかし、その先には、ご本人の可能性を広げ、ご家族も安心できる、新しい日常が待っています。
千葉県で障がい者グループホームをお探しなら、「千葉SMILEHOUSE」へご相談ください
私たち「千葉SMILEHOUSE」は、千葉市を中心に、利用者一人ひとりの個性と自立を尊重した、温かい家庭のようなグループホームを運営しています。
経験豊富なスタッフが、24時間体制であなたの生活をサポート
美味しい手作りの食事と、清潔で快適な住環境
就労支援や日中活動の相談にも親身に対応
「まずは話だけでも聞いてみたい」
「施設の中を一度見てみたい」
どんな些細なご質問やご不安でも構いません。制度の申請方法から、実際のご入居まで、私たちが責任を持って、あなたとご家族に寄り添いながらサポートさせていただきます。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。あなたの笑顔あふれる新生活を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間: 月曜~日曜 8:00~17:00
留守電の場合はお名前とグループホームについてご質問がある旨をお伝えいただけますと、折り返しご連絡させていただきます。
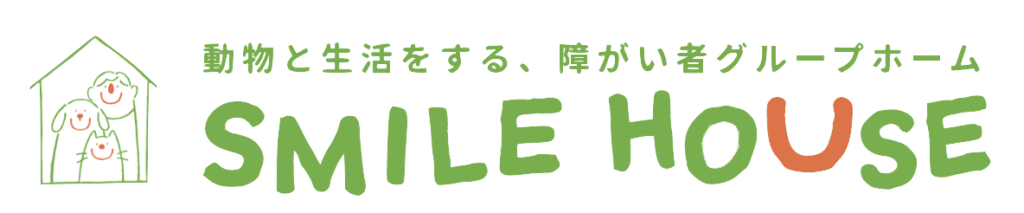
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
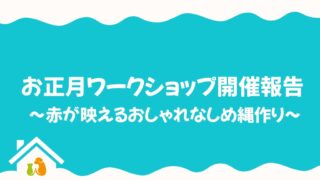 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告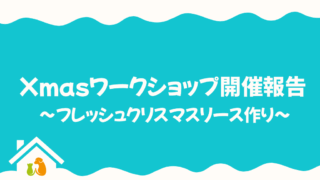 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告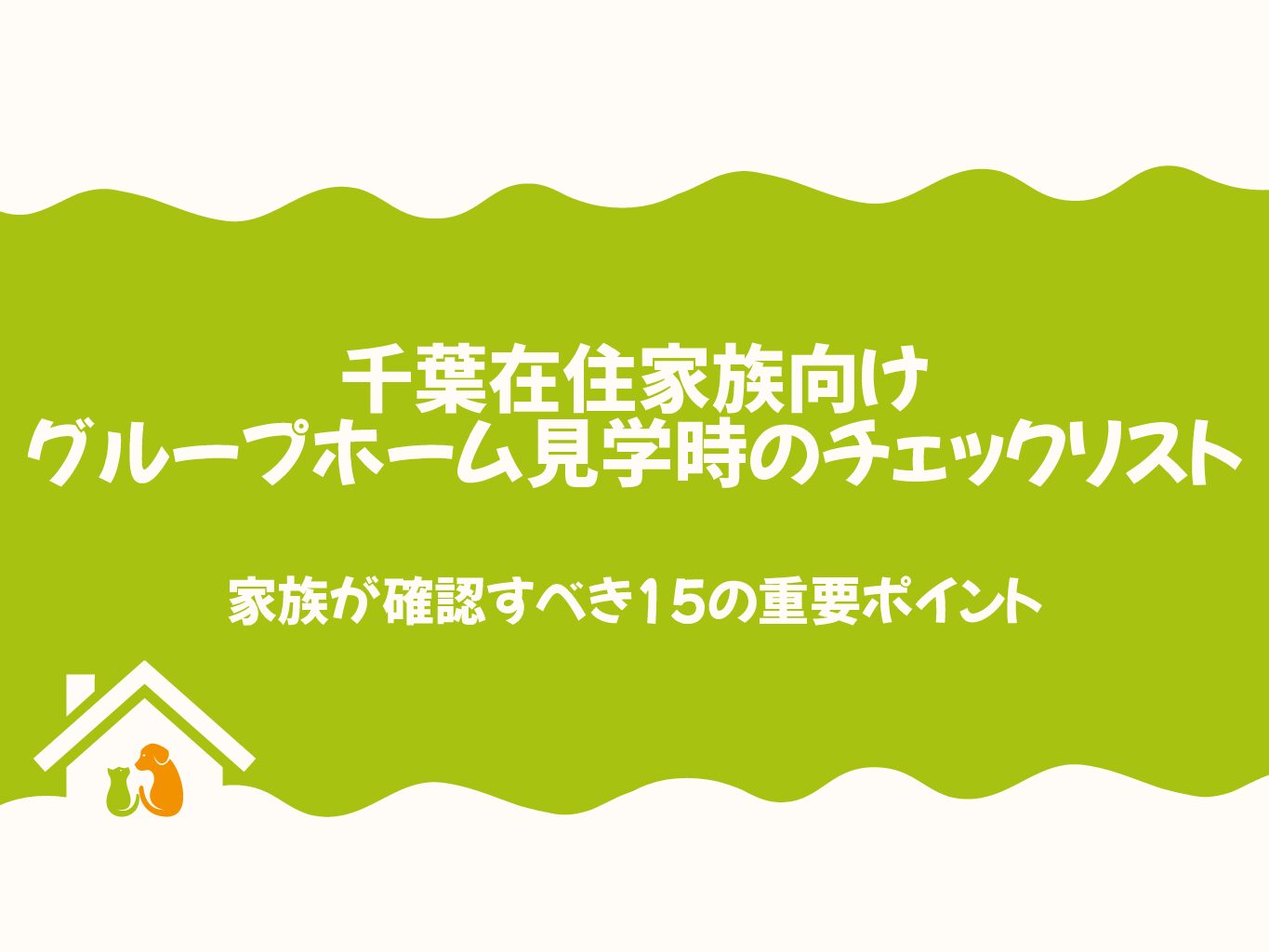 情報発信2025年11月27日千葉在住家族向け:グループホーム見学時のチェックリスト|家族が確認すべき15の重要ポイント
情報発信2025年11月27日千葉在住家族向け:グループホーム見学時のチェックリスト|家族が確認すべき15の重要ポイント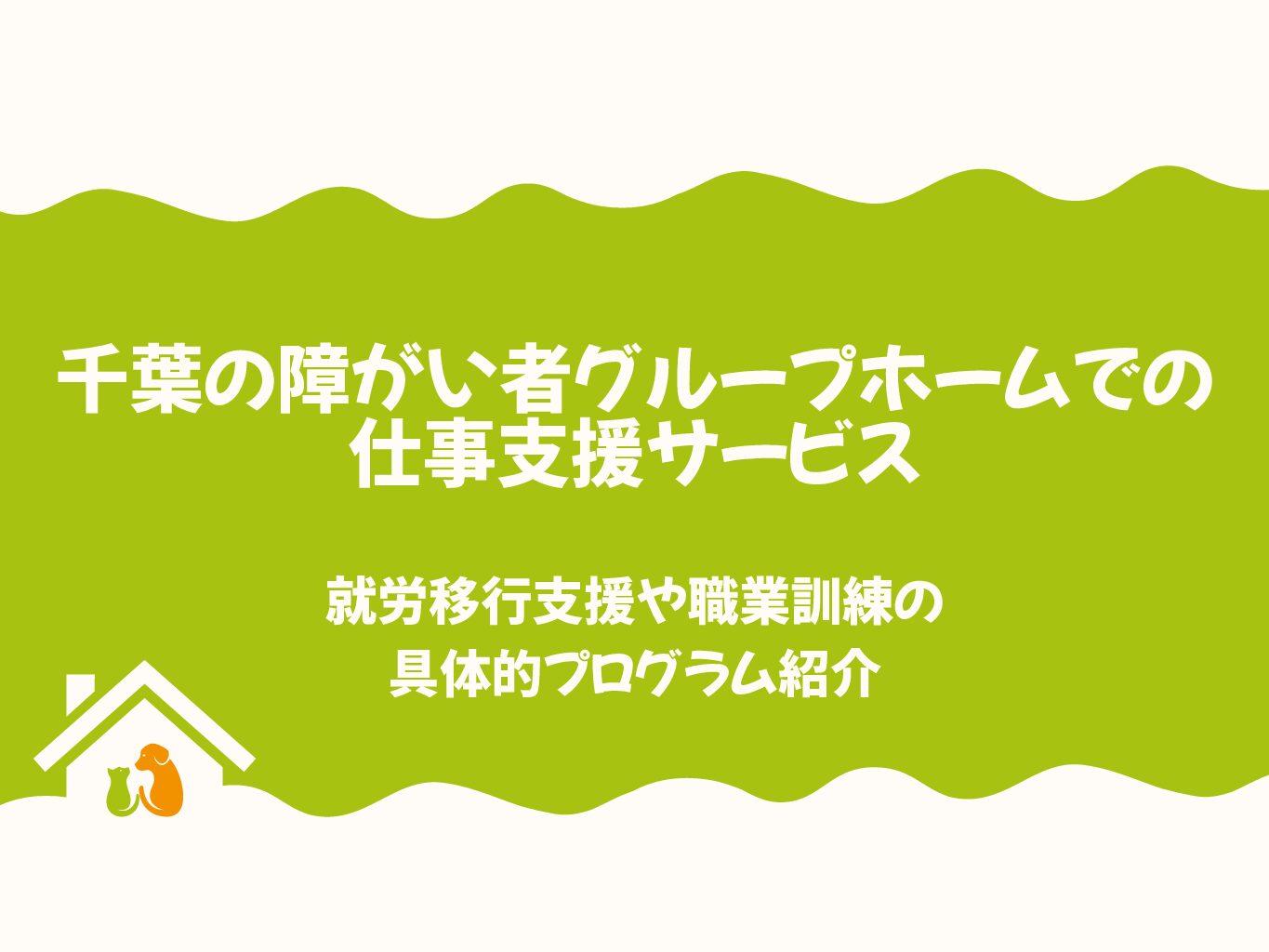 情報発信2025年11月20日千葉の障がい者グループホームでの仕事支援サービス|就労移行支援や職業訓練の具体的プログラム紹介
情報発信2025年11月20日千葉の障がい者グループホームでの仕事支援サービス|就労移行支援や職業訓練の具体的プログラム紹介