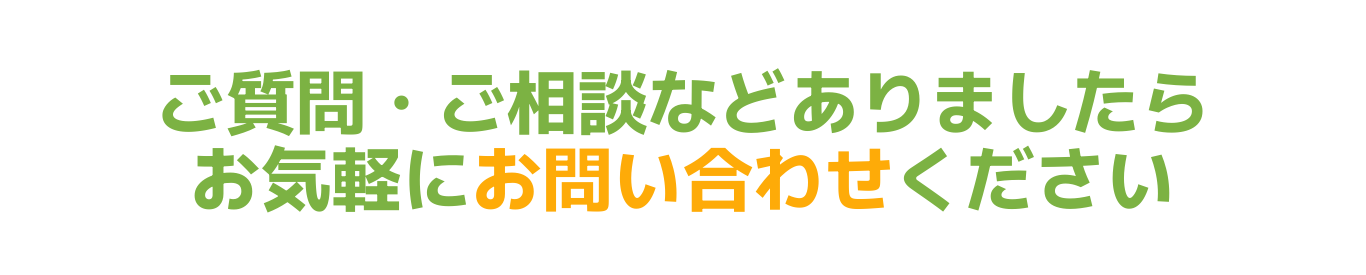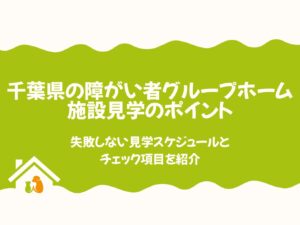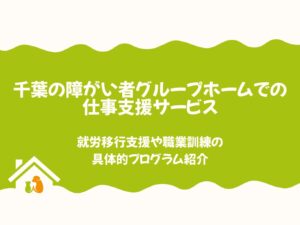千葉県の障がい者グループホームで受けられる支援まとめ|就労支援から医療・リハビリサービスまで網羅
【はじめに】
千葉県の障がい者グループホームへの入居を検討されているあなたへ。
「地域で自立した生活を送りたいけれど、一人暮らしには少し不安がある…」
「家族に頼らず、自分らしい暮らしを見つけたい」
「日中の活動や仕事と両立しながら、安心して暮らせる場所はないだろうか?」
ご本人様も、そして支えるご家族様も、様々な期待と同時に、多くの疑問や不安を抱えていらっしゃることでしょう。
千葉県には、そんな一人ひとりの想いに寄り添い、自立した生活をサポートするための「障がい者グループホーム」が数多く存在します。
この記事では、千葉県の障がい者グループホームで受けられる支援の全体像を、就労支援から医療・リハビリサービスに至るまで、網羅的にご紹介します。
この記事を最後までお読みいただくことで、あなたやご家族が抱える疑問や不安が解消され、ご自身に最適なグループホームを見つけるための、確かな一歩を踏み出すことができるはずです。
1. 障がい者グループホームとは?千葉県での支援概要
1-1. グループホームの基本的な役割と仕組み
障がい者グループホーム(共同生活援助)とは、障がいのある方が地域社会の中で、ごく普通の暮らしを送ることを目的とした住まいのことです 。
専門のスタッフ(世話人や生活支援員)のサポートを受けながら、数人の仲間と一緒に共同生活を送ります。
完全に一人で生活するのではなく、かといって施設のように管理されるのでもない、「自立」と「安心」のバランスが取れた暮らしの形、それが障がい者グループホームの大きな役割です。
食事の準備や掃除などの家事を共同で行ったり、日中は職場や作業所に通ったりと、一人ひとりのペースに合わせた生活を築いていくことができます。
1-2. 千葉県における障がい者グループホームの特徴
千葉県では、県や各市町村が連携し、障がいのある方の地域生活を積極的に支援しています 。
特に千葉市をはじめとする主要都市では、多様なニーズに応えるべく、様々な特色を持つ障がい者グループホームが増えています 。
例えば、ペット共生型のグループホームや、重度の障がいや医療的ケアに対応したホーム、ITに特化した就労支援を行うホームなど、ご自身のライフスタイルや目標に合わせて選べるのが千葉県の魅力です。
また、県の支援事業により、事業者向けの研修や利用者への家賃補助なども充実しており、質の高いサービスが提供される環境が整っています 。
1-3. 対象となる障がいの種類(身体・知的・精神・難病)
障がい者グループホームは、特定の障がい種別に限定されるものではありません。
身体障がい、知的障がい、精神障がい(統合失調症、うつ病、てんかんなど)、そして発達障がいのある方々が利用されています。
また、障害者総合支援法の対象となる369疾病の難病をお持ちの方も入居が可能です 。
大切なのは、障がいの種別や手帳の有無だけでなく、「地域で自立した生活を送りたい」というご本人の意思です。
障害支援区分(後述します)の認定を受けることで、必要な支援を受けながらグループホームでの生活をスタートできます。
2. グループホームで受けられる基本的な生活支援
障がい者グループホームでは、入居者一人ひとりが安心して快適な毎日を送れるよう、きめ細やかな生活支援が提供されます。
ここでは、千葉県の多くのグループホームで共通して受けられる基本的な支援内容をご紹介します。
2-1. 日常生活の支援内容(食事・入浴・排泄の介護)
- 食事の提供・支援: 栄養バランスの取れた食事が朝夕提供されるのが一般的です。ご自身で調理を希望される方には、スタッフが調理方法をアドバイスしたり、一緒に買い物に行ったりといった支援も行います。アレルギーや病状に合わせた個別対応も相談可能です。
- 入浴・排泄の支援: お一人での入浴や排泄が難しい方には、必要に応じてスタッフが介助を行います。安全に入浴できるよう見守りをしたり、着替えを手伝ったりと、ご本人のプライバシーに配慮しながら、尊厳を大切にしたサポートを心がけています。
- 清掃・洗濯の支援: 居室や共用スペースの掃除、洗濯など、身の回りの環境を清潔に保つための支援を行います。ご自身でできることは主体的に行ってもらい、難しい部分をスタッフがサポートすることで、自立した生活習慣を身につけていくことを目指します。
2-2. 健康管理と服薬管理のサポート
毎日の健康状態のチェック(検温、血圧測定など)や、体調不良時の医療機関への連絡・連携を行います。
また、薬の飲み忘れや飲み間違いがないよう、スタッフが服薬の管理・支援をすることも重要な役割です。
ご家族や主治医と情報を共有し、常に最適な健康状態を維持できるよう努めます。
2-3. 金銭管理と生活相談の支援
お給料や年金の管理、計画的な金銭の使用について、ご本人やご家族の希望に応じてサポートします。
お小遣い帳の付け方のアドバイスから、公共料金の支払い支援まで、安心して金銭を管理できるようお手伝いします。
また、日々の生活の中での悩みや人間関係のトラブル、将来への不安など、どんな些細なことでも気軽に相談できる体制を整えています。
2-4. 24時間見守り体制と緊急時対応
多くのグループホームでは、夜間もスタッフが常駐またはオンコール体制を整えており、24時間安心して過ごせる環境を提供しています 。
夜間の急な体調不良や、災害などの緊急時にも、迅速かつ適切に対応できる体制が整っていることは、ご本人様にとってもご家族様にとっても大きな安心材料となるでしょう。
3. グループホームの種類とサービス内容の違い
千葉県の障がい者グループホームは、提供されるサービス内容によって主に4つのタイプに分けられます 。ご自身の障がいの程度や、日中の過ごし方、目指すライフスタイルによって最適なタイプが異なります。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったホームを選びましょう。
| 種類 | 特徴と主な対象者 |
| 介護サービス包括型 | 特徴: 主に夜間や休日に、グループホームのスタッフが食事や入浴などの介護サービスを直接提供します 。比較的障がいの程度が重い方でも安心して生活できる体制が整っています。 対象者: 障害支援区分3以上の方で、日常生活において比較的多くの介護や支援を必要とする方。 |
| 外部サービス利用型 | 特徴: 日常生活の相談や家事などの支援はグループホームのスタッフが行いますが、専門的な介護(入浴介助など)は、入居者自身が契約した外部の居宅介護事業所から提供されます 。 対象者: 障害支援区分2以下の方で、必要な時に外部の専門サービスを利用しながら自立した生活を送りたい方。 |
| 日中サービス支援型 | 特徴: 24時間スタッフが常駐し、夜間の支援だけでなく、日中もグループホーム内で生活する方への支援体制が手厚いタイプです 。短期入所(ショートステイ)の受け入れも可能な事業所が多いのが特徴です。 対象者: 重度の障がいや加齢により、日中も常に支援が必要な方や、退院後の移行先として手厚いサポートを求める方。 |
| サテライト型住居 | 特徴: グループホーム本体の近くにあるアパートなどで、一人暮らしに近い形で生活します。何か困ったことがあれば、本体のスタッフがすぐに駆けつけてくれる安心感があります 。 対象者: 将来的な一人暮らしを目指しており、そのステップとして一定の支援を受けながら生活の練習をしたい方。 |
4. 就労支援とキャリア形成のサポート
「働きながら地域で暮らしたい」という想いを実現するため、千葉県の多くの障がい者グループホームでは、就労に関する手厚いサポートを提供しています。
①就労先との連絡調整と通勤支援
グループホームのスタッフが、ご本人の就労先(一般企業や福祉的就労の事業所)と定期的に連絡を取り合い、勤務状況や体調の変化などを情報共有します。
職場での悩みや課題があれば、ご本人と企業の間に入って調整役を担うこともあります。
また、安定して通勤できるよう、交通機関の利用方法を一緒に練習したり、必要に応じて送迎を行ったりする支援もあります。
②就労移行支援事業所との連携体制
就労移行支援事業所は、一般企業への就職を目指す障がいのある方に対し、職業訓練や就職活動のサポートを行う場所です。
グループホームでは、これらの事業所と密に連携し、「住まい」と「日中活動」の両面から利用者を支えます。
例えば、事業所で学んだビジネスマナーをグループホームの生活の中で実践してみるなど、一貫した支援を受けながら就職を目指すことができます。
③就労継続支援(A型・B型)との組み合わせ
就労継続支援は、すぐに一般企業で働くことが難しい場合に、支援を受けながら働くことができる福祉サービスです。
雇用契約を結ぶA型と、比較的自分のペースで作業を行うB型があります。
グループホームで生活しながら、日中は近隣の就労継続支援事業所に通う、というライフスタイルを送っている方は非常に多く、安定した収入とやりがいのある日中活動を両立させています。
④就労定着支援による職場定着のフォロー
就職はゴールではなく、スタートです。就職後に長く働き続けるためには、様々なサポートが必要になります。就労定着支援は、就職後6ヶ月を経過した方を対象に、生活リズムの構築、対人関係の調整、仕事上の課題解決などをサポートするサービスです。グループホームのスタッフも、就労定着支援の担当者と連携し、利用者が職場で孤立することなく、安心して働き続けられるよう支えていきます。
5. 医療・リハビリサービスとの連携体制
障がい者グループホームでの安心な暮らしは、地域の医療機関との密な連携があってこそ成り立ちます。
特に千葉県千葉市などでは、医療的ケアに対応できるグループホームも増えており、多様なニーズに応える体制が整いつつあります。
①訪問看護ステーションとの医療連携
多くのグループホームでは地域の訪問看護ステーションと契約を結んでいます 。看護師が定期的にグループホームを訪問し、入居者の健康チェック、服薬管理、医療的な処置、健康相談などを行います。
日々の健康状態を専門的な視点から見守ることで、病気の早期発見や重症化の予防につなげます。
②医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養等)への対応
喀痰吸引(たんの吸引)や経管栄養(胃ろうなど)といった医療的ケアが必要な方でも、入居できるグループホームが増えています 。看護師と連携し、研修を受けた介護職員がケアを行える体制を整えている事業所もあります。入居を希望する場合は、対応可能な医療的ケアの種類や範囲について、事前にグループホームに確認することが重要です。
③通院同行と医療機関との連絡調整
定期的な通院が必要な場合、スタッフが付き添いを行います。一人での通院が不安な方も、スタッフが一緒なら安心です。また、診察に同席し、医師からの説明をご本人に分かりやすく伝えたり、ご本人の状態を医師に正確に報告したりと、ご本人と医療機関との橋渡し役を担います。
④リハビリテーション支援の提供
グループホームの生活そのものが、身体機能や生活能力の維持・向上を目指すリハビリテーションの一環と捉えられています。それに加え、理学療法士(PT)や作業療法士(OT)といったリハビリの専門家と連携し、個別のリハビリ計画に基づいた支援を提供するグループホームもあります。
⑤精神科病院との連携と症状管理
精神障がいのある方にとって、症状の安定は地域生活を継続する上で非常に重要です。多くのグループホームでは、地域の精神科病院やクリニックと緊密に連携しています。定期的な通院への同行はもちろん、精神科訪問看護を利用して、日々の様子の変化を専門家と共有し、症状が悪化する前兆を早期に捉え、適切な対応ができる体制を整えています。
6. 相談支援事業所の役割とサービス等利用計画
障がい福祉サービスを利用するためには、「相談支援事業所」との連携が不可欠です。少し難しく聞こえるかもしれませんが、あなたらしい生活を実現するための「頼れるパートナー」を見つけることだと考えてください。
①相談支援専門員によるトータルサポート
相談支援事業所には、「相談支援専門員」という資格を持つ専門家がいます 。彼らは、障がいのある方やそのご家族からの様々な相談に応じ、必要な情報提供やアドバイスを行います。グループホーム探しはもちろん、日中活動の場の選定、各種手続きのサポートなど、利用できるサービスを総合的にコーディネートしてくれる、まさに「福祉のコンシェルジュ」のような存在です。
②サービス等利用計画の作成と定期的な見直し
障がい福祉サービスを利用するためには、一人ひとりの希望や目標、心身の状態に合わせて、「サービス等利用計画」を作成する必要があります 。この計画書は、相談支援専門員がご本人やご家族と面談を重ね、「どのような生活を送りたいか」「そのためにどのような支援が必要か」を一緒に考えながら作成します。グループホームへの入居も、この計画に基づいて進められます。計画は一度作ったら終わりではなく、生活の変化に合わせて定期的に見直し(モニタリング)が行われます。
③関係機関との連絡調整とコーディネート
相談支援専門員は、ご本人を中心に、グループホーム、市町村の役所、医療機関、就労支援事業所など、関わる全ての機関と連絡を取り合い、チームとしてご本人を支えるための調整役を担います 。情報がスムーズに共有されることで、一貫性のある、質の高い支援を受けることができます。
④地域移行支援と地域定着支援
長期間入院・入所していた方が地域での生活に移行する際には「地域移行支援」、単身での生活が不安定な方には「地域定着支援」といった専門のサポートもあります 。相談支援事業所はこれらのサービスも活用し、グループホームへの入居だけでなく、その後の安定した地域生活までを見据えた支援を行います。
7. 千葉県独自の支援制度と家賃補助
障がい者グループホームで生活する上で、経済的な負担は大きな関心事の一つです。国や千葉県、そして千葉市などの各市町村では、家賃負担を軽減するための様々な補助制度を設けています 。
①特定障害者特別給付費(国の家賃補助)
これは国の制度で、「補足給付」とも呼ばれます。グループホームの家賃のうち、月額1万円を上限として国が補助してくれる制度です。対象となるのは、市町村民税が非課税の世帯の方などです。
②千葉県障害者グループホーム等支援事業
千葉県では、グループホームの安定的な運営とサービス向上のため、独自の支援事業を行っています 。これにより、事業者は質の高い支援を提供するための基盤を強化でき、結果として入居者の安心な暮らしにつながっています。
③千葉市・船橋市・市川市など市町村独自の家賃助成
国の補助に加えて、多くの市町村が独自の家賃助成制度を設けています。
- 千葉市: 千葉市障害者グループホーム等運営補助事業など、運営を支える制度があります 。
- 市川市: 市川市障害者グループホーム等入居者家賃助成金制度があり、国の補助(1万円)に加えて、市が定めた額を上乗せして助成が受けられます 。
- 松戸市: 障害者グループホーム等家賃助成金があり、家賃額に応じて助成が受けられます 。
これらの制度は市町村によって内容が異なるため、お住まいの地域の障害福祉課に確認することが大切です。
④生活保護との併用と費用負担の軽減策
グループホームの費用は、生活保護制度を利用して支払うことも可能です。生活保護を受給している場合、家賃相当額が住宅扶助として、食費や光熱費などが生活扶助として支給されます。収入が少ない方でも、これらの制度を組み合わせることで、経済的な心配をせずにグループホームでの生活を始めることができます。
8. グループホーム入居の条件と利用手続き
「自分もグループホームに入れるのだろうか?」「手続きが難しそう…」そんな不安をお持ちの方のために、入居の条件と手続きの流れを分かりやすく解説します。
①入居対象者と障害支援区分について
グループホームの入居対象者は、基本的に18歳以上の障がいのある方です(一部、15歳以上も可)。入居にあたっては、「障害支援区分」の認定を受けることが一般的です 。障害支援区分とは、障がいの特性や心身の状態に応じて、どのくらいの支援が必要かを行政が判定するものです。区分1から区分6まであり、数字が大きいほど必要な支援の度合いが高いことを示します。多くのグループホームでは、この区分を目安に入居の可否や提供する支援内容を判断します。
②入居までの流れ(相談~契約まで)
- 相談: まずは、お住まいの市町村の障害福祉課や、相談支援事業所に相談しましょう 。
- 障害支援区分の申請・認定: サービスの利用に必要な障害支援区分の認定を受けます。
- 障害福祉サービス受給者証の交付: 区分認定後、グループホーム(共同生活援助)の利用が記載された「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
- グループホーム探し・見学: 相談支援専門員と一緒に、希望に合うグループホームを探し、実際に見学に行きます。
- 体験入居: 契約の前に、数日間~数週間程度の体験入居を行い、実際の生活を体験します。
- 契約・入居: ご本人、ご家族、グループホーム、相談支援専門員で最終的な意思確認を行い、契約を結んで入居となります。
③必要な書類と障害福祉サービス受給者証の取得
手続きには、主に以下の書類が必要になります。
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 障害福祉サービス受給者証
- サービス等利用計画(案)
- 健康診断書 など
「障害福祉サービス受給者証」は、いわば「福祉サービスを利用するためのパスポート」です。これがないとサービスの利用ができないため、早めに市町村の窓口で申請手続きを行いましょう。
④体験入居の活用方法
体験入居は、グループホームとのミスマッチを防ぐための非常に重要な機会です。食事の味や他の入居者との相性、スタッフの雰囲気、周辺の環境など、パンフレットだけでは分からないことを肌で感じることができます。不安な点や疑問点は、この期間中に遠慮なくスタッフに質問しましょう。
9. グループホームの費用相場と負担軽減制度
グループホームでの生活にかかる費用は、大きく分けて「サービス利用料」と「実費負担」の2つがあります。
9-1. 月額費用の内訳(家賃・食費・光熱費・サービス利用料)
- 家賃: 居室の家賃です。千葉県内では3万円~5万円程度が相場ですが、前述の家賃補助制度を利用できます。
- 食費・光熱費など: 3万円~5万円程度が目安です。食材費や共用部分の水道光熱費などが含まれます。
- サービス利用料(訓練等給付費): 障害福祉サービスの自己負担額です。所得に応じて負担上限月額が定められています。
- その他の実費: 居室の電気代、電話代、日用品費などは個人負担となります。
合計すると、家賃補助などを利用した後の実質的な負担額は、月額6万円~8万円程度になることが多いです。
9-2. 所得に応じた利用者負担額の上限
サービス利用料の自己負担額は、世帯の所得に応じて以下のように上限が定められています。
| 所得区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外(所得割16万円以上) | 37,200円 |
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は「一般2」に該当する場合でも「一般1」の区分と同様の負担額となります。
9-3. 食費等実費負担の減免措置
低所得の世帯に対しては、食費や光熱費などの実費負担についても減免措置が設けられている場合があります。詳しい条件は市町村によって異なるため、障害福祉課の窓口で確認しましょう。
9-4. 千葉県内の費用相場と予算の立て方
千葉県内のグループホームの費用は、立地や設備、提供されるサービスによって様々です 。ご自身の障害年金や給料などの収入と、各種補助制度を考慮して、無理なく生活できる範囲で予算を立てることが大切です。相談支援専門員が資金計画の相談にも乗ってくれますので、一人で悩まずに相談してください。
10. 千葉県内のグループホームの探し方
自分に合ったグループホームを見つけるためには、どうすれば良いのでしょうか。主な探し方をご紹介します。
①市町村の障害福祉課への相談
最も基本的な相談窓口です。お住まいの地域の障害福祉を管轄する部署(名称は市町村により異なります)に行けば、地域のグループホームのリストや情報を提供してくれます。
②相談支援事業所の活用方法
前述の通り、相談支援専門員はグループホーム探しのプロフェッショナルです。インターネットには載っていない情報を持っていたり、各事業所の雰囲気や評判を詳し く知っていたりすることも多いです。あなたの希望を丁寧にヒアリングし、最適なホームをいくつか提案してくれます。
③千葉県障害者グループホーム等支援事業の支援ワーカー
千葉県では、グループホームへの入居を希望する方やそのご家族を支援するための専門のワーカーを配置しています 。地域ごとの担当ワーカーが、グループホーム探しから入居後の生活まで、様々な相談に応じてくれます。
④見学時のチェックポイント
見学は、入居後の生活を具体的にイメージするための大切な機会です。以下の点をチェックしてみましょう。
- 居室: 日当たり、広さ、収納、プライバシーは保たれているか。
- 共用スペース: 清潔か、アットホームな雰囲気か。
- スタッフ: 入居者への接し方、表情はどうか。質問に丁寧に答えてくれるか。
- 他の入居者: どのような方が生活しているか、表情は明るいか。
- 食事: メニューや食事の雰囲気はどうか。
- ルール: 門限や外泊、飲酒などのルールは自分に合っているか。
- 周辺環境: 最寄り駅からの距離、スーパーやコンビニ、医療機関は近くにあるか。
11. グループホーム利用者とご家族の声
ここでは、実際にグループホームで生活を始めた方の喜びの声をご紹介します。
①就労と生活の両立を実現したケース(Aさん・30代・知的障がい)
「実家暮らしの頃は、親に頼ってばかりで、仕事の疲れもあって家のことは何もできませんでした。グループホームに入居してからは、スタッフさんに励まされながら、少しずつ料理や掃除ができるように。今では日中、就労継続支援B型事業所で働き、休日は趣味の絵を描いて楽しく過ごしています。自分の力で生活できているという自信が、仕事への意欲にもつながっています。」
②医療的ケアを受けながら安心して暮らすケース(Bさん・50代・難病)
「退院後、一人暮らしは無理だと諦めかけていた時、医療的ケアに対応しているこのグループホームに出会いました。訪問看護師さんが定期的に来てくれるし、夜間もスタッフさんがいるので、体調が不安な時もすぐに相談できて心強いです。同じように病気と向き合う仲間がいることも、大きな支えになっています。」
③自立に向けて一歩ずつ進んでいるケース(Cさんのご家族様)
「精神的に不安定になりがちだった息子が、グループホームに入ってから本当に穏やかになりました。スタッフの方々が本人のペースを尊重し、根気強く関わってくださるおかげです。金銭管理や服薬も自分でできるようになり、少しずつ自信を取り戻している姿を見るのが、親として何より嬉しいです。将来はサテライト型住宅に移ることを目標に、頑張っています。」
【まとめ】
千葉県で安心して暮らせるグループホーム選びのポイント
ここまで、千葉県の障がい者グループホームで受けられる様々な支援内容について詳しく見てきました。最後に、あなたに合ったグループホームを選ぶための大切なポイントを3つにまとめます。
- 支援内容と自分に合ったサービス類型をじっくり選ぶこと
ご自身の障がいの状況や、日中の過ごし方、将来の目標などを整理し、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」「サテライト型」の中から、最も自分らしい生活が送れるタイプを選びましょう。 - 経済的負担を軽減する制度を最大限に活用すること
国や千葉県、お住まいの市町村には、家賃補助などの手厚い支援制度があります。これらの制度を上手に活用することで、経済的な不安を大きく軽減できます。諦める前に、まずは相談することが大切です。 - 一人で悩まず、相談窓口を積極的に利用すること
市町村の障害福祉課や相談支援事業所は、あなたの味方です。分からないこと、不安なことは、どんな些細なことでも遠慮なく相談してください。専門家と一緒に、じっくりと時間をかけて、あなたにとって最高の住まいを見つけていきましょう。
千葉県千葉市で障がい者グループホームをお探しなら、私たち「千葉SMILEHOUSE」にご相談ください。
私たち千葉SMILEHOUSEは、千葉市を中心に、利用者様一人ひとりの「自分らしい暮らし」を全力でサポートする障がい者グループホームを運営しています。
経験豊富なスタッフが、あなたの状況やご希望を丁寧にお伺いし、最適な支援プランをご提案します。就労支援や医療機関との連携体制も万全です。
「まずは話だけ聞いてみたい」
「どんな場所か一度見てみたい」
そんな方も大歓迎です。グループホームへの入居は、ご本人様とご家族様にとって、人生の大きな一歩です。その大切な一歩を、私たちが心を込めてお手伝いします。
見学は随時受け付けております。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせはこちらから
受付時間: 月曜~日曜 8:00~17:00
留守電の場合はお名前とグループホームについてご質問がある旨をお伝えいただけますと、折り返しご連絡させていただきます。
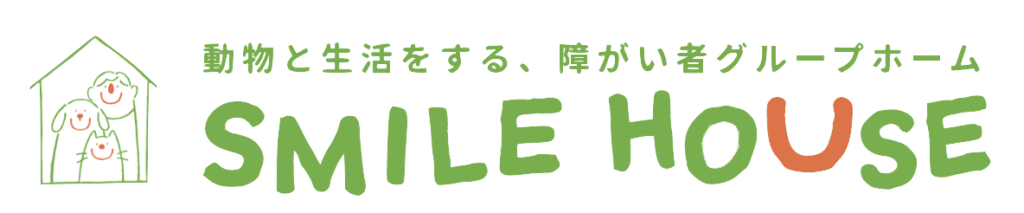
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
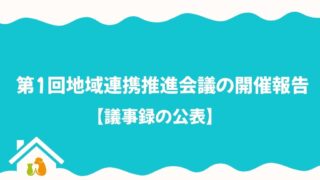 お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告
お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告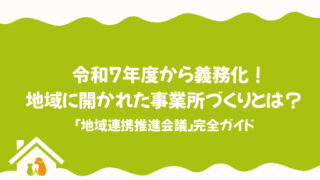 情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?
情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?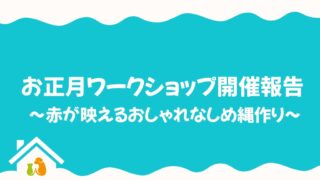 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告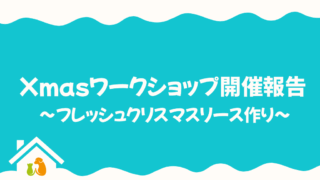 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告