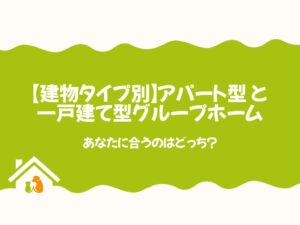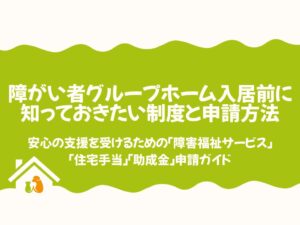障がい者グループホーム利用中の家族の役割|適切な距離感と支援方法について
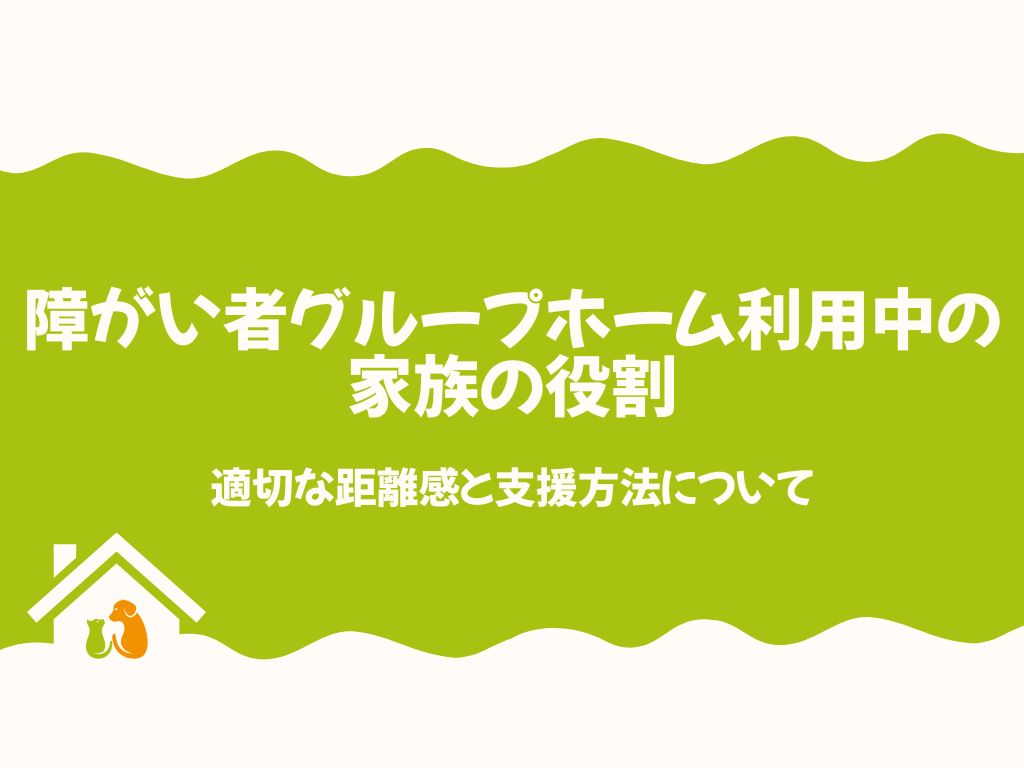
【はじめに】
「この子が自分たちがいなくなった後、どうやって暮らしていけばいいのだろう…」
「毎日続く介護に、心も体も疲れ果ててしまった…」
「本人の自立を願っているけれど、本当に一人で大丈夫だろうか…」
障がい者グループホームの利用を考え始めるとき、ご家族の胸には、期待と同時にさまざまな不安が渦巻いているのではないでしょうか。それは、お子さんを深く愛し、その将来を真剣に考えているからこそ抱く、ごく自然な感情です。
この記事では、そんな複雑な思いを抱えるご家族に向けて、障がい者グループホーム利用後の「家族の役割」や「ご本人との適切な距離感」、そして「具体的な支援方法」について、詳しく、そして温かく解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、以下のことがわかります。
- グループホーム利用後の家族の新しい役割
- ご本人との健全な距離感の保ち方
- スタッフと連携した効果的なサポート方法
- ご家族自身の心のケアと生活の再構築
- 将来を見据えた「親なき後」への備え
グループホームは、決してご家族との関係を断つ場所ではありません。
むしろ、ご家族が「介護者」から「一番の応援者」へと役割を変え、より豊かで新しい関係を築くためのスタートラインです。
この記事が、ご家族の皆様が抱える不安を少しでも和らげ、前向きな一歩を踏み出すための道しるべとなれば幸いです。
1. 家族が抱える不安と期待
障がい者グループホームの利用は、ご本人にとって大きな一歩であると同時に、長年支えてきたご家族にとっても、人生の大きな節目となります。
まずは、多くのご家族が経験する「きっかけ」と「複雑な気持ち」について、一緒に考えていきましょう。
1-1 グループホーム利用を考えるきっかけ
ご家族がグループホームの利用を考え始めるきっかけは、決して一つではありません。
多くの場合、複数の要因が重なり合って、本格的な検討へとつながっていきます。
- 親の高齢化と「親亡き後」の不安
「自分たちが元気なうちはいいけれど、この先どうなるんだろう?」これは、多くのご家族が抱える切実な悩みです。ご両親が高齢になるにつれて、将来的な介護への体力的な不安や、万が一のことがあった後のご本人の生活に対する心配が大きくなるのは当然のことです。 - 家族の介護負担と限界
日々のサポートは、愛情深くとも、心身ともに大きな負担を伴います。特に、24時間体制での見守りが必要な場合や、ご家族が仕事と介護の両立に悩んでいる場合、「もう限界かもしれない」と感じる瞬間は誰にでも訪れます。 - 障がいのある方の自立への願い
「同年代の他の子たちのように、親元を離れて自分の力で生活する経験をさせてあげたい」。いつまでも親がそばにいるのではなく、一人の大人として社会と関わり、自立した生活を送ってほしいという願いも、グループホーム利用を後押しする大きな動機となります。
1-2 家族が感じる複雑な気持ち
グループホームの必要性を頭では理解していても、心が追いつかないこともあります。特に、「罪悪感」や「寂しさ」は、多くのご家族が経験する感情です。
- 「手放すような罪悪感」への向き合い方
「施設に入れるなんて、かわいそうなのでは?」「親として無責任だろうか?」といった罪悪感を感じてしまうかもしれません。しかし、グループホームの利用は「手放す」ことではありません。お子さんの自立という成長段階を、専門家のサポートを得ながら応援する「新しい支援の形」なのです。 - 「最後まで面倒を見られなかった」という思いの整理
「最後まで自分の手で」という強い責任感から、自分を責めてしまうこともあるでしょう。ですが、ご家族だけで全てを抱え込むことが、必ずしもご本人にとって最善とは限りません。専門的なケアと適切な環境の中で、ご本人が新たな可能性を見出すことも多くあります。 - 自立支援と愛情の関係性
愛情があるからこそ、心配で手放せない。その気持ちは痛いほどわかります。しかし、本当の愛情とは、時には距離を置き、失敗を恐れずに挑戦する機会を与える「見守る勇気」を持つことでもあるのです。
2. 障がい者グループホームにおける家族の基本的役割
グループホームでの生活が始まると、ご家族の役割は大きく変化します。
これまでの「介護者」「保護者」という立場から、ご本人の人生を応援する「サポーター」へとシフトしていくのです。
2-1 グループホームとは「住まい」であること
まず大切なのは、グループホームを「施設」ではなく、ご本人の「新しい家」として捉えることです。
- 施設ではなく生活の場としての理解
グループホームは、治療や管理を目的とした場所ではありません。他の利用者やスタッフと交流しながら、地域の一員として自分らしい生活を送るための「住まい」です。そこには、ご家庭と同じように、生活のリズムやルールが存在します。 - 利用者の自己決定権の尊重
グループホームでは、ご本人の「こうしたい」「こうなりたい」という意思が何よりも尊重されます。食事の時間、休日の過ごし方、挑戦してみたいことなど、ご本人が主体的に決定する場面が増えていきます。ご家族は、その決定を温かく見守り、応援する姿勢が大切になります。 - 家族から「応援者」への役割変化
ご家族は、介護の主役から、ご本人の人生を応援する一番の「ファン」へと変わります。日々の身の回りの世話はスタッフに任せ、ご家族は、ご本人が安心して挑戦できるよう、精神的な支えとなることが最も重要な役割となるのです。
2-2 家族が担うべき主要な役割
「応援者」としての家族には、具体的にどのような役割が求められるのでしょうか。
- 精神的な支えとしての存在
環境が変わり、不安を感じているのはご本人も同じです。定期的な面会や電話で「いつもあなたのことを気にかけているよ」「頑張っているね」と伝えることは、ご本人にとって何よりの心の支えになります。 - グループホームスタッフとの連携
スタッフは、ご本人の日々の暮らしを支えるパートナーです。ご本人の家庭での様子や特性、好きなことや苦手なことなどをスタッフと共有し、逆にグループホームでの様子を教えてもらうことで、より良いサポート体制を築くことができます。 - 利用者の成長を見守る姿勢
親元を離れたことで、これまでできなかったことができるようになったり、新しい一面が見えたりと、ご本人の成長に驚かされることがきっとあるでしょう。その小さな変化や成長を見つけ、認め、一緒に喜ぶことが、ご本人の自信につながります。
3. 適切な距離感の保ち方
グループホームの利用を機に、ご家族が最も悩むのが「適切な距離感」かもしれません。
愛情が深いほど、つい干渉しすぎてしまったり、逆にどう関わっていいか分からなくなったりしがちです。
3-1 「親離れ・子離れ」の重要性
障がい者グループホームの利用は、ご本人とご家族双方にとっての「親離れ・子離れ」の機会と捉えることができます。
- 過保護と無関心の間のバランス
心配のあまり頻繁に連絡したり、身の回りのことを先回りしてやってしまったりするのは「過保護」です。これでは、ご本人の自立の機会を奪ってしまいます。一方で、すべてをスタッフ任せにして無関心になるのも問題です。大切なのは、ご本人の力を信じ、必要な時に手を差し伸べられる「見守る」スタンスです。 - 新しい親子関係の構築
これまでの「保護する側とされる側」という関係から、一人の大人同士として向き合う、新しい親子関係を築くチャンスです。お互いの人生を尊重し、対等な立場で語り合える関係を目指しましょう。 - 自立を促すための「見守る勇気」
ご本人が失敗したり、少し困ったりしていても、すぐに手や口を出さずに見守る「勇気」が必要です。自分で考えて行動し、時には失敗から学ぶ経験こそが、本当の自立心を育むのです。
3-2 具体的な距離感の調整方法
では、具体的にどのように距離感を調整すればよいのでしょうか。
- 面会・連絡頻度の適正化
入居当初は不安で毎日でも顔を見たくなるかもしれませんが、まずは週に1回程度の面会や電話を目安にしてみましょう。ご本人が新しい環境や人間関係に慣れるための時間と空間を確保してあげることが大切です。 - 利用者の状況に応じた柔軟な対応
もちろん、ルールは絶対ではありません。ご本人がホームシックになったり、体調を崩したりした時には、面会頻度を増やすなど、状況に応じて柔軟に対応しましょう。逆に、ご本人が新しい生活を楽しんでいるようであれば、少し距離を置いて見守ることも必要です。
3-3 家族が陥りがちな問題と解決策
良かれと思ってしたことが、かえってご本人のためにならないケースもあります。
- 過度な介入による自立阻害
「部屋が散らかっているから」と勝手に片付けてしまったり、「食事が偏っているから」と差し入れをしすぎたりする行為は、ご本人が生活スキルを学ぶ機会を奪ってしまいます。まずはスタッフに相談し、ご本人が自分でできるようになるためのサポート方法を一緒に考えましょう。 - 毎日の連絡・面会の見直し
毎日の連絡が習慣になっていると、ご本人がグループホームの活動に集中できなかったり、ご家族への依存心が抜けなくなったりすることがあります。少し寂しくても、連絡の頻度を徐々に減らしていく勇気を持ちましょう。 - スタッフとの認識のずれへの対処
「もっとこうしてほしいのに」という思いと、スタッフの対応にズレを感じることもあるかもしれません。その際は、感情的に不満をぶつけるのではなく、「家ではこうしていたのですが、こちらではどうでしょうか?」と、相談する形でコミュニケーションをとることが、良好な関係を築くコツです。
4. 効果的な家族支援の方法
ご家族が「応援者」として、ご本人とグループホームを効果的にサポートするための具体的な方法をご紹介します。
4-1 グループホームスタッフとの連携
スタッフは、ご家族にとって最も頼りになるパートナーです。密な連携を心がけましょう。
- 定期的な情報共有の重要性
多くのグループホームでは、連絡帳や定期的な面談の機会が設けられています。ご家庭での出来事(法事、親戚の集まりなど)や、ご本人の体調の変化などをこまめに伝えることで、スタッフもご本人の心の動きを察知しやすくなります。 - 個別支援計画への参画
グループホームでは、利用者一人ひとりに合わせた「個別支援計画」を作成します。この計画を立てる際に、ご家族として「こんなことができるようになってほしい」「こんな生活を送ってほしい」という希望を伝えることは非常に重要です。 - 相談しやすい関係づくり
日頃からスタッフと良好なコミュニケーションをとり、「ちょっとしたことでも相談できる」関係を築いておくことが大切です。感謝の気持ちを言葉で伝えるなど、お互いを尊重する姿勢が信頼関係の基礎となります。
4-2 利用者への具体的なサポート
日常生活のサポートはスタッフが中心となりますが、ご家族だからこそできるサポートもあります。
- 季節の衣替えや日用品の補充
季節の変わり目に一緒に服を買いに行ったり、衣替えを手伝ったりすることは、良いコミュニケーションの機会になります。また、ご本人が好きなシャンプーや化粧品など、こだわりのある日用品を一緒に買いに行くのも良いでしょう。 - 通院の付き添い(必要に応じて)
定期的な通院や、専門的な医療機関を受診する際には、ご家族の付き添いが求められる場合があります。ご本人の病歴や体質を最もよく知るご家族が同席することで、医師とのやり取りもスムーズになります。 - 外出や一時帰宅での家族との時間
週末や連休に一緒に外食したり、買い物に出かけたり、実家に一時帰宅したりする時間は、ご本人にとってもご家族にとっても、かけがえのないリフレッシュの時間となります。
4-3 緊急時・トラブル時の対応
万が一の事態に備えて、緊急時の対応についても確認しておきましょう。
- 24時間連絡体制の確認
多くのグループホームでは、夜間や休日でも対応できる緊急連絡体制が整っています。連絡先や連絡方法を事前に確認し、いつでも連絡が取れるようにしておきましょう。 - 医療機関との連携体制
かかりつけの医療機関や、緊急時に搬送される病院など、グループホームがどのような医療機関と連携しているのかを把握しておくと安心です。 - 家族として備えておくべきこと
ご本人の保険証やお薬手帳のコピー、緊急連絡先リストなどをまとめたファイルを作成し、グループホームとご家族で共有しておくと、いざという時に迅速に対応できます。
5. 家族自身のケアと生活の再構築
ご本人のグループホーム利用は、ご家族自身の生活を見つめ直す大きなきっかけにもなります。
長年の介護生活から解放され、ご自身の時間を取り戻す時期です。
5-1 介護負担からの解放感への対処
これまで介護に費やしてきた時間が急になくなることで、戸惑いや寂しさを感じるかもしれません。
- 急激な生活の変化への適応
長年の生活リズムが急に変わることで、心にぽっかりと穴が空いたように感じることがあります。これは「燃え尽き症候群」にも似た状態で、決して珍しいことではありません。焦らず、ゆっくりと新しい生活に慣れていきましょう。 - 空虚感や喪失感の受け止め方
「自分はもう必要とされていないのではないか」といった喪失感を感じることもあるかもしれません。しかし、それはご本人が自立への一歩を踏み出した証でもあります。役割が変わっただけで、ご家族の存在価値がなくなったわけではありません。 - 新しい生活リズムの確立
これまで介護に充てていた時間を、意識的に自分のために使ってみましょう。朝ゆっくりとコーヒーを飲む、好きな音楽を聴くなど、小さなことからでも構いません。
5-2 家族自身の人生設計
ご自身の人生を、もう一度楽しむための計画を立ててみませんか。
- 趣味や社会活動への復帰
介護のために諦めていた趣味や、友人との旅行、地域の活動などに、もう一度挑戦してみましょう。新しい生きがいを見つけることが、心の充実につながります。 - キャリアの継続・新たなチャレンジ
介護離職をしていた方は、再就職を考える良い機会かもしれません。また、仕事を続けてきた方も、これまで以上にキャリアに集中したり、新しいスキルを学んだりする時間が生まれます。 - 夫婦関係や家族関係の再構築
お子さん中心だった生活から、夫婦二人の時間を取り戻すきっかけにもなります。一緒に食事に出かけたり、共通の趣味を始めたりして、新たな関係を築いていきましょう。
5-3 家族同士のネットワーク活用
同じ境遇にある他の家族とつながることは、大きな力になります。
- 家族会・保護者会への参加
多くのグループホームでは、家族会や保護者会が定期的に開催されています。積極的に参加し、情報交換の場として活用しましょう。 - 同じ立場の家族との情報交換
同じような悩みや不安を共有し、共感し合える仲間がいることは、何よりの心の支えになります。他のご家族がどのように関わっているのかを知ることも、参考になるでしょう。 - 先輩家族からのアドバイス活用
少し先に入居したご家族の「先輩」からのアドバイスは、非常に実践的で役立つことが多いです。困ったときには、気軽に相談してみましょう。
6. 将来を見据えた準備と心構え
グループホームでの生活は、「親亡き後」の生活を見据えた第一歩でもあります。安心して将来を託すために、今からできる準備を進めていきましょう。
6-1 「親亡き後」への備え
ご家族が元気なうちに、法的な手続きや経済的な準備を整えておくことが大切です。
- 成年後見制度の活用検討
判断能力が十分でない場合に、ご本人に代わって財産管理や身上監護(生活や治療に関する契約など)を行う人を選ぶ制度です。ご家族が後見人になることも、弁護士などの専門家に依頼することも可能です。 - 経済的な準備(信託・生命保険等)
ご本人が将来生活に困らないよう、財産を遺す方法を検討しましょう。親が亡くなった後に保険金が支払われる生命保険や、財産を信頼できる人や機関に託して管理・運用してもらう「信託」などの方法があります。 - 支援者ネットワークの構築
ご家族以外にも、ご本人のことを理解し、いざという時に頼れる支援者を増やしておくことが重要です。グループホームのスタッフはもちろん、相談支援専門員や地域の民生委員など、様々な人とのつながりを作っておきましょう。
6-2 長期的な視点での支援計画
ご本人のライフステージに合わせて、支援計画も更新していく必要があります。
- ライフステージに応じた目標設定
20代、30代、40代と年齢を重ねる中で、ご本人の興味や関心、必要な支援は変化していきます。その時々の状況に合わせて、個別支援計画を見直し、新たな目標を設定していくことが大切です。 - 将来の住まい・就労の検討
グループホームでの生活が安定したら、日中の活動(就労継続支援B型事業所など)についても考えていきましょう。また、将来的に一人暮らしやサテライト型住居へステップアップする可能性なども、ご本人の希望を聞きながら検討します。 - 地域との関係性維持
グループホームは地域社会の中にあります。地域のイベントに参加したり、近所のお店で買い物をしたりと、地域とのつながりを持ち続けることが、ご本人の社会的な孤立を防ぎ、豊かな生活につながります。
6-3 本人の意思決定支援
どのような準備や計画も、主役はご本人です。常にご本人の意思を尊重する姿勢を忘れないでください。
- 本人の希望・意向の聞き取り
「将来どうなりたい?」「どんな生活がしたい?」と、ご本人の希望を丁寧に聞き取りましょう。言葉で表現するのが苦手な場合は、絵や写真を使うなど、ご本人に合った方法でコミュニケーションをとることが大切です。 - 自己決定を尊重する姿勢
たとえご家族の考えと違っても、ご本人が自分で決めたことであれば、まずはその意思を尊重し、応援してあげましょう。自己決定の経験を積み重ねることが、自信と責任感を育みます。 - 将来のビジョン共有
ご本人が描く将来のビジョンと、ご家族が願う将来像をすり合わせ、共有しておくことが、円満な支援の鍵となります。
7. よくある質問と解決策
最後によくあるご質問とその解決策をご紹介します。
7-1 面会・訪問に関するルール
面会や訪問には、共同生活ならではのルールがあります。
- 訪問時間の制限への理解
他の利用者の生活リズムや、スタッフの業務(食事準備、入浴支援など)に配慮するため、面会時間が決められていることがほとんどです。事前に時間を確認し、ルールを守りましょう。 - 宿泊時の事前許可の必要性
ご家族がグループホームに宿泊することは、原則としてできませんが、一時帰宅は可能です。一時帰宅や外出の際は、食事の準備などの都合があるため、事前にスタッフに伝えておくのがマナーです。 - 共同生活への配慮
大声での会話や、他の利用者の居室を無断で覗くなどの行為は避けましょう。グループホームは、ご本人だけでなく、他の利用者にとっても大切な「我が家」であることを忘れないでください。
7-2 費用・契約に関する注意点
契約時には、費用に関する項目をしっかりと確認しましょう。
- 利用料金の内訳確認
家賃、食費、水道光熱費、日用品費など、月々の支払いが何にいくらかかるのか、内訳を詳しく確認しましょう。 - 追加費用の把握
月額費用以外に、医療費、理美容代、個人的な買い物代など、別途必要となる費用についても把握しておきましょう。 - 退去条件の理解
どのような場合に退去となるのか(医療的なケアが必要になった場合など)、契約書で退去要件を必ず確認しておくことが大切です。
7-3 トラブル・不満への対応
スタッフとの間でトラブルや不満が生じた場合の対処法です。
- 要望の伝え方(相談形式での依頼)
「~してくれない」と否定的に伝えるのではなく、「~していただけると、本人がもっと安心して過ごせるのですが」のように、相談・提案の形で伝えると、相手も受け入れやすくなります。 - スタッフとの信頼関係構築
日頃から感謝の気持ちを伝え、良好な関係を築いておくことが、いざという時の円滑なコミュニケーションにつながります。 - 適切な距離感での関わり方
スタッフも人間です。利用者と適切な距離感を保ちながら支援を行っています。過度な要求や個人的な連絡先の交換などは避け、節度ある関係を保ちましょう。
【まとめ】
障がい者グループホームの利用は、ご本人とご家族にとって、新しい関係性を築くための素晴らしい機会です。
①グループホーム利用がもたらす変化
- 家族関係の質的向上: 介護の負担が減ることで、心に余裕が生まれ、純粋に親子としての時間を楽しめるようになります。
- 利用者の成長への新たな気づき: ご家庭では見られなかったご本人の新たな一面や成長を発見し、喜びを感じることができます。
- より自然で対等な親子関係: 「お世話する・される」関係から、互いを一人の大人として尊重し合える、より対等な関係へと変化していきます。
②理想的な家族の在り方
これからのご家族の役割は、ご本人の人生の「伴走者」です。ご本人の一番の理解者として、時には励まし、時にはそっと見守り、人生の節目節目で一緒に悩み、喜ぶ。そんな存在であり続けることが、ご本人にとって最大の力となるでしょう。
③今後のアクション
もし、この記事を読んでグループホームへの関心が深まったなら、ぜひ次の一歩を踏み出してみてください。
- グループホームの見学・体験: 百聞は一見に如かず。実際にいくつかのグループホームを見学し、雰囲気やスタッフの様子をご自身の目で確かめることが非常に重要です。
- 家族での話し合い: ご本人を含め、ご家族全員で将来について話し合う時間を作りましょう。
- 専門家への相談: お住まいの地域の相談支援事業所などに相談すれば、専門的なアドバイスや、ご本人に合ったグループホームの情報を提供してもらえます。
障がい者グループホームの利用は、決して寂しいお別れではありません。それは、ご本人とご家族が、それぞれの人生を豊かに歩み始めるための、希望に満ちた新しいスタートです。
「千葉SMILEHOUSE」では、ご利用を検討されているご本人様とご家族様の不安に、とことん寄り添います。
「何から始めたらいいかわからない」
「うちの子に合うグループホームはあるだろうか?」
「費用はどのくらいかかるの?」
どんな些細なことでも構いません。まずは、あなたのお話をお聞かせください。経験豊富なスタッフが、一つひとつの疑問に丁寧にお答えし、ご家族にとって最善の道筋を一緒に考えます。
アットホームな環境で、利用者さんたちが生き生きと暮らす様子をぜひご覧ください。無理な勧誘は一切いたしませんので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
あなたとご家族が、笑顔で新しい一歩を踏み出せる日を、心から応援しています。
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
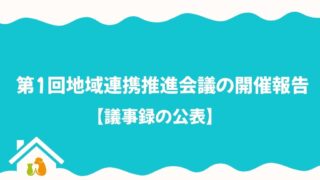 お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告
お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告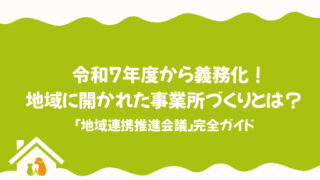 情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?
情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?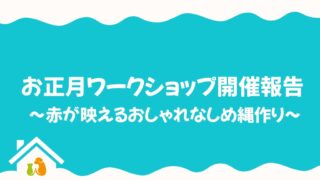 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告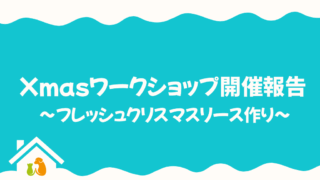 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告