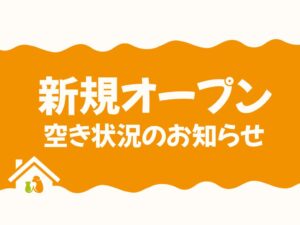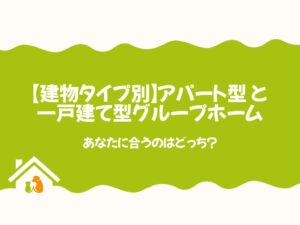障がい者グループホーム・在宅介護・施設入所の違いを徹底比較|選び方の完全ガイド
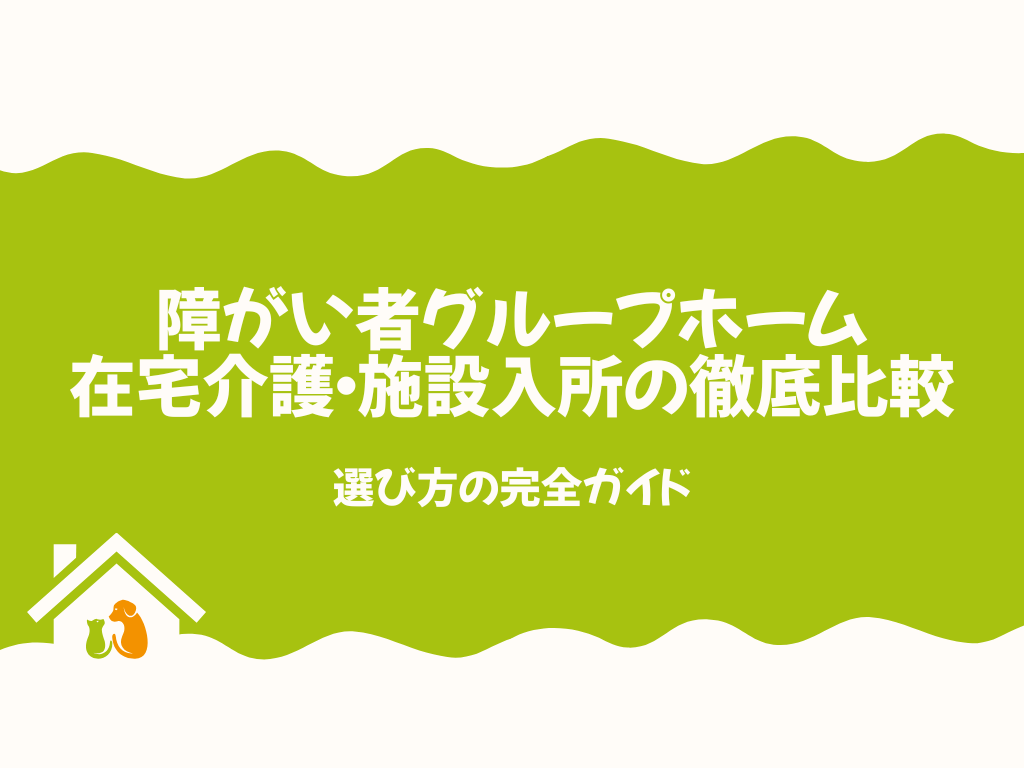
【はじめに】
障がいのある方の「自分らしい暮らし」を見つけるために
障がいをお持ちのご本人、そして日々その生活を支えるご家族の皆様。
「将来、どこで、どのように暮らしていくのが一番良いのだろう?」
「本人の自立を支えたいけれど、何から始めればいいか分からない…」
「今の生活を続けることに、少しずつ不安を感じ始めている…」
こうした想いを抱えながら、障がいのある方の住まいについて、様々な情報を集めていらっしゃるのではないでしょうか。選択肢は一つではありません。
障がい者グループホームでの共同生活、住み慣れた家での在宅介護、そして手厚い支援が受けられる施設入所。
それぞれの選択肢に、それぞれの良さがあり、同時に考慮すべき点も存在します。
この記事では、これら三つの暮らしのカタチを、どこよりも分かりやすく、そして誠実に比較・解説していきます。
この記事を最後までお読みいただくことで、それぞれの選択肢の明確な違いが分かります。メリット・デメリットを深く理解し、ご自身やご家族の状況に合った選択肢が見えてきます。
将来の暮らしを具体的に考えるための、確かなヒントを得られます。一人で、あるいはご家族だけで悩みを抱え込む必要はありません。
この記事が、皆様にとって最適な「自分らしい暮らし」を見つけるための、信頼できる道しるべとなることを心から願っています。どうぞ、安心して読み進めてください。
1. 三つの選択肢「障がい者グループホーム」「在宅介護」「施設入所」の基本的な違いと特徴
まず初めに、それぞれの暮らしの形がどのようなものなのか、基本的な特徴を整理してみましょう。
この違いを理解することが、最適な選択への第一歩となります。
1-1. 障がい者グループホーム(共同生活援助)とは?
障がい者グループホームは、障がいのある方が地域社会の中で、他の利用者と共同で生活を送る「住まいの場」です。
世話人や生活支援員といった専門スタッフのサポートを受けながら、食事の準備や掃除などを分担し、自立した日常生活を送ることを目指します。
キーワードは「地域での自立」
アパートや一軒家といった、ごく普通の住居で生活するため、地域社会から孤立することなく、自分らしい暮らしを築いていくことができます。スーパーへの買い物や地域のイベントへの参加など、社会とのつながりを持ちやすいのが大きな特徴です。
対象者と利用条件
主に知的障がい、精神障がい、身体障がいのある方が対象で、共同生活を送ることに支障がない方が利用します。
施設入所とは異なり、比較的軽度から中度の障がいの方が多く利用されています。
1-2. 在宅介護とは?
在宅介護は、その名の通り、障がいのある方がこれまで通り住み慣れたご自宅で生活を継続し、ご家族が中心となって介護を行う形です。
必要に応じて、訪問介護(ホームヘルプ)やデイサービス(通所支援)といった外部の福祉サービスを組み合わせて利用します。
キーワードは「住み慣れた安心感」
長年暮らしてきた自宅での生活は、ご本人にとって何よりの安心感につながります。家族との時間を大切にしながら、ご自身のペースで生活を送ることができるのが最大のメリットです。
家族による介護と専門サービスの組み合わせ
介護の主体はご家族となりますが、すべてを家族だけで抱え込むわけではありません。
ケアマネージャーや相談支援専門員と相談しながら、必要なサービスを計画的に利用し、家族の負担を軽減していくことが可能です。
1-3. 施設入所(障がい者支援施設)とは?
施設入所(正式には「障害者支援施設」)は、常時介護を必要とする障がいのある方が入所し、24時間体制で手厚い支援を受けることができる施設です。
主に、日中の活動を支援する「生活介護」と、夜間の住まいの場を提供する「施設入所支援」を一体的に提供します。
キーワードは「手厚い専門的ケア」
医師や看護師、理学療法士などの専門職が配置されている場合が多く、医療的ケアや専門的なリハビリテーションが必要な方にとって、安心して生活できる環境が整っています。
入所条件と対象者
原則として、障がい支援区分が4以上(50歳以上の方は区分3以上)の方で、常時介護を必要とする方が対象となります。
障がい者グループホームや在宅介護での生活が困難な、比較的重度の障がいのある方が利用の中心です。
2. 障がい者グループホームのメリット・デメリット
地域での自立を目指す障がい者グループホーム。その具体的なメリットと、知っておくべきデメリットを詳しく見ていきましょう。
2-1. グループホームのメリット
家庭的で温かい環境での共同生活
大規模な施設入所とは異なり、少人数(通常4〜10名程度)での共同生活のため、家庭的でアットホームな雰囲気の中で暮らすことができます。
他の利用者やスタッフと家族のように関わり合いながら、孤独を感じることなく、温かい人間関係を築くことができます。
自立に向けた段階的サポート
「すべてをやってもらう」のではなく、「できることは自分でやる」ことを基本としています。掃除や洗濯、食事の準備などをスタッフのサポートを受けながら行うことで、生活能力が向上し、自信がつきます。これは、将来の一人暮らしやさらなる自立に向けた、非常に重要なステップとなります。
地域との交流と社会参加機会
障がい者グループホームは地域の中にあります。近所の方との挨拶や、地域のイベントへの参加、日中の就労先への通勤など、ごく自然な形で社会と関わることができます。
施設入所のように閉鎖的な環境ではなく、社会の一員としての実感を得やすい点は大きなメリットです。
費用負担の軽減(障がい基礎年金内での生活が可能)
家賃や光熱費、食費などの実費はかかりますが、国の家賃補助制度などを利用できる場合が多く、施設入所に比べて費用を抑えられる傾向にあります。多くの方が、障がい基礎年金の範囲内で生活費をまかなっており、経済的な自立も目指せます。
将来の一人暮らしへのステップとして活用
「いずれは一人暮らしをしたい」と考える方にとって、グループホームは最適な練習の場です。
共同生活を通じて生活スキルを身につけ、金銭管理などを学びながら、自信を持って次のステップに進む準備ができます。
2-2. グループホームのデメリット
共同生活による人間関係の課題
他の利用者との共同生活は、メリットであると同時に、人によってはストレスの原因にもなり得ます。生活リズムや価値観の違いから、人間関係のトラブルが発生する可能性はゼロではありません。
医療的ケアの制限
多くの障がい者グループホームでは、看護師が常駐しているわけではないため、日常的な医療的ケア(経管栄養、喀痰吸引など)が必要な方の受け入れは難しい場合があります。施設入所に比べ、医療サポート体制は限定的です。
空き状況による入居待ちの可能性
近年、障がい者グループホームの需要は高まっており、地域によっては希望する施設にすぐに入居できない「入居待ち」が発生しています。計画的に施設を探し始めることが重要です。
プライバシーの制約
個室が用意されている場合がほとんどですが、リビングや食堂、浴室などは共用です。在宅介護のように、完全にプライベートな空間と時間を確保することは難しい側面があります。
3. 在宅介護のメリット・デメリット
住み慣れた自宅で暮らし続ける在宅介護。その魅力と、向き合わなければならない課題について掘り下げます。
3-1. 在宅介護のメリット
住み慣れた環境での安心感
長年過ごしてきた自分の家、自分の部屋で暮らせることは、ご本人にとって何物にも代えがたい精神的な安定をもたらします。環境の変化によるストレスがなく、リラックスして過ごせるのが最大のメリットです。
家族との密接な関係維持
常に家族がそばにいるため、コミュニケーションが密になり、強い絆を維持することができます。家族の愛情を感じながら生活できることは、ご本人の心の支えとなります。
経済的負担の軽減(施設入所と比較して)
施設入所のように高額な入所費用がかからず、必要な介護サービス費と生活費で暮らせるため、経済的な負担を抑えられる場合があります。
個々のペースに合わせた生活
食事の時間や就寝時間など、施設のルールに縛られることなく、ご本人の体調や気分に合わせた柔軟な生活を送ることができます。
3-2. 在宅介護のデメリット
介護者(家族)の肉体的・精神的負担
在宅介護を選択する上で、最も大きな課題となるのがこの点です。
24時間365日、介護から解放される時間はなく、特に夜間の対応や入浴介助などは大きな肉体的負担となります。
また、「自分がしっかりしなければ」というプレッシャーや、自分の時間が持てないことによる精神的なストレスは計り知れません。
専門的ケアの提供限界
家族は介護のプロではありません。障がいの特性に応じた専門的なケアや、医療的ケアの提供には限界があります。ご本人の状態が変化した際に、適切な対応が難しい場面も出てきます。
緊急時対応の困難さ
介護者である家族が急病で倒れたり、事故に遭ったりした場合、ご本人のケアが途絶えてしまうリスクがあります。すぐに代わりの支援を見つけることは容易ではありません。
介護者の社会参加機会の制限
介護に多くの時間を費やすことで、介護者が仕事を辞めざるを得なくなったり、友人との交流や趣味の時間がなくなったりと、社会から孤立してしまうケースも少なくありません。
適切な介護技術習得の必要性
安全で快適な介護を行うためには、正しい知識と技術が必要です。ボディメカニクス(身体の負担が少ない介護技術)などを学ばなければ、介護者が腰を痛めるなど、共倒れのリスクも高まります。
4. 施設入所のメリット・デメリット
専門的なケアが24時間受けられる施設入所。手厚いサポートの裏側にある側面も見ていきましょう。
4-1. 施設入所のメリット
24時間体制の専門的介護・医療サポート
施設入所の最大のメリットは、介護・医療の専門スタッフが24時間常駐していることです。夜間の急な体調変化や、日常的な医療的ケアが必要な場合でも、迅速かつ適切な対応が可能です。障がい者グループホームや在宅介護では難しい、手厚いケアが受けられます。
家族の介護負担軽減
介護のすべてを専門スタッフに任せられるため、ご家族は身体的・精神的な負担から解放されます。「親」や「子」としての関係に集中でき、心に余裕を持ってご本人と接することができるようになります。
安全で安心な生活環境
施設内はバリアフリー化されており、転倒防止の手すりやナースコールなどが完備されています。利用者一人ひとりの状態に合わせた安全な環境で、安心して生活を送ることができます。
リハビリテーション等の充実した専門サービス
理学療法士や作業療法士などによる専門的なリハビリテーションや、様々なレクリエーション活動が提供されており、心身機能の維持・向上を目指すことができます。
4-2. 施設入所のデメリット
環境変化による精神的負担
住み慣れた自宅や地域を離れ、新しい環境と人間関係の中で生活を始めることは、ご本人にとって大きな精神的ストレスとなる場合があります。
家族との距離が生まれやすい
在宅介護に比べ、家族と会える時間が限られてしまうため、物理的・心理的な距離が生まれやすい側面があります。面会時間の制約がある施設も少なくありません。
集団生活による個別性の制約
食事や入浴の時間など、一日のスケジュールがある程度決まっているため、ご本人のペースに合わせた生活は難しくなります。集団生活のルールに従う必要があります。
地域との繋がりの希薄化
生活の場が施設内に限定されがちなため、障がい者グループホームのように地域社会との日常的な関わりを持つ機会は少なくなります。
5. 費用面での比較
どの暮らしの形を選ぶかにおいて、費用は非常に重要な要素です。ここでは、それぞれの費用構造と、利用できる制度について解説します。
5-1. それぞれの費用
| 選択肢 | 主な費用項目 | 費用の特徴 |
|---|---|---|
| 障がい者グループホーム | ・家賃 ・食費、光熱水費 ・日用品費 ・サービス利用料(1割負担) |
国の家賃補助制度あり。障がい基礎年金の範囲内で生活できるケースが多い。 |
| 在宅介護 | ・介護サービス利用料(1割負担) ・住宅改修費(手すり設置など) ・福祉用具レンタル・購入費 ・日々の生活費 |
サービス利用量で変動。住宅改修には補助金が出る場合がある。 |
| 施設入所 | ・サービス利用料(1割負担) ・食費、光熱水費 ・居住費 ・その他日用品費など |
費用は高額になりがちだが、所得に応じた負担上限月額が定められている。 |
5-2. 経済的サポート制度
どの選択肢を選んでも、利用者の負担が大きくなりすぎないよう、様々な制度が用意されています。
利用者負担上限月額
所得に応じて、1か月に支払うサービス利用料(1割負担分)の上限額が定められています。
家賃補助(特定障害者特別給付費)
障がい者グループホームに入居する低所得の方を対象に、月額最大1万円の家賃補助が支給されます。
住宅改修費の助成
在宅介護のために手すりの設置や段差の解消などを行う際、費用の一部が助成されます。経済的な不安についても、市町村の窓口や相談支援専門員に相談することで、利用できる制度を詳しく教えてもらえます。
6. ライフステージ別の選び方ガイド
「結局、私たちの場合はどれがいいの?」その疑問に答えるため、状況別の選び方のヒントをご紹介します。
6-1. 障がいの程度・支援区分による選択
軽度(区分1~3)で自立意欲がある方
障がい者グループホームが最も適している可能性が高いでしょう。日中は就労支援事業所に通い、夜間や休日に共同生活を送ることで、自立に向けたスキルと自信を育むことができます。
中重度(区分4以上)で一定の身の回りのことができる方
医療的ケアが常時必要でなければ、手厚いサポート体制のある障がい者グループホームも選択肢になります。在宅介護と組み合わせながら、ショートステイでグループホームを体験してみるのも良い方法です。
重度で常時介護や医療的ケアが必要な方
24時間体制の専門的なケアが不可欠な場合は、施設入所が最も安心できる選択肢となります。
6-2. 年齢・将来設計による選択
若年期(10代~30代)
親元からの自立や、社会参加を目指す時期です。障がい者グループホームで共同生活のルールや生活スキルを学び、将来のステップに繋げるという視点が重要です。
中年期(40代~50代)
生活の安定と継続性がテーマになります。ご本人の希望を尊重しつつ、親御さんの高齢化も見据え、障がい者グループホームや施設入所への移行を具体的に検討し始める時期かもしれません。
高齢期(60代以上)
ご本人の加齢に伴う身体機能の低下や、医療ニーズの高まりが考慮点となります。在宅介護を継続しつつ、医療連携の強い障がい者グループホームを探したり、穏やかな終の棲家として施設入所を選択したりと、医療・介護の手厚さが選択の鍵となります。
6-3. 家族状況による選択
介護者が若く、時間に余裕がある場合
在宅介護を主軸に、ショートステイなどを活用して介護者の休息を確保しながら生活を組み立てることが可能です。
介護者が高齢、または仕事で多忙な場合
無理に在宅介護を続けると、共倒れのリスクが高まります。ご家族の生活を守るためにも、障がい者グループホームや施設入所を積極的に検討することが、結果的にご本人のためにもなります。
7. 実際の選択プロセス
では、具体的にどのように行動すれば良いのでしょうか。相談から決定までの流れを解説します。
7-1. 相談から決定まで
市町村窓口での相談
すべてのスタートはここからです。お住まいの市町村の障がい福祉担当窓口へ行き、「将来の住まいについて相談したい」と伝えましょう。制度の概要や、地域の事業所について情報提供してもらえます。
相談支援専門員との連携
障がい福祉サービスを利用するには、「サービス等利用計画」の作成が必要です。これを手伝ってくれるのが相談支援専門員です。専門的な視点から、ご本人やご家族の希望に沿った最適なプランを一緒に考えてくれます。
各施設の見学・体験利用
パンフレットだけでは分からないことがたくさんあります。障がい者グループホームや施設入所を検討する場合は、必ず見学に行きましょう。施設の雰囲気、スタッフや他の利用者の様子、周辺環境などを自分の目で確かめることが何よりも重要です。
可能であれば、ショートステイを利用した「お試し体験」をおすすめします。
7-2. 必要な手続きと準備
障がい支援区分の認定
福祉サービスを利用するための「パスポート」のようなものです。まだ認定を受けていない場合は、市町村に申請します。
サービス等利用計画の作成
相談支援専門員と共に、どのサービスをどのくらい利用するかを計画します。
契約手続き
利用したい事業所が決まったら、重要事項の説明を受け、納得した上で契約を結びます。
8. よくある質問(Q&A)
皆様からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 途中で選択を変更することは可能ですか?
A. はい、可能です。
例えば、在宅介護から障がい者グループホームへ、あるいは障がい者グループホームでの生活が難しくなり施設入所へ、といった変更は珍しくありません。
ご本人の心身の状態やご家族の状況の変化に応じて、その時々で最適な暮らしの形を柔軟に再検討していくことが大切です。
Q. 緊急時にはどの選択肢が最適でしょうか?
A. 介護者が急に入院するなど、予測不能な緊急事態では、迅速に受け入れてくれる場所が必要です。
日頃から地域のショートステイ(短期入所)が可能な障がい者グループホームや施設をいくつかリストアップし、いざという時のために相談しておくと安心です。
Q. 複数のサービスを組み合わせることは可能ですか?
A. はい、可能です。
例えば、「平日の日中は就労支援B型事業所に通い、それ以外の時間は在宅介護で過ごし、週末だけ障がい者グループホームのショートステイを利用する」といった組み合わせもできます。
相談支援専門員と相談し、オーダーメイドの支援計画を立てましょう。
Q. 家族が反対する場合の説得方法を教えてください?
A. まずは、なぜ反対するのか、その理由(「世間体が悪い」「冷たい親だと思われたくない」「本人が可哀想」など)をじっくり聞きましょう。
その上で、この記事で解説したような各選択肢のメリット・デメリットを客観的に伝え、在宅介護を続けた場合の将来的なリスク(共倒れなど)も冷静に話し合うことが重要です。
何より、「本人の自立と幸せのため」という共通のゴールを確認し、一緒に施設見学に行くなど、家族全員で考える機会を持つことが解決の糸口になります。
【まとめ】
あなたに最適な選択を見つけるために
ここまで、障がい者グループホーム、在宅介護、施設入所という三つの選択肢について、詳しく比較・解説してきました。
どの選択肢が一番良い、という絶対的な正解はありません。ご本人とご家族にとっての「最適な暮らし」が、一番の正解です。
選択のポイント総まとめ
最後に、後悔しない選択をするための最も大切なポイントを3つお伝えします。
①本人の意思と希望の重要性
主役は、あくまで障がいのあるご本人です。「本人がどうしたいのか」「どのような暮らしを送りたいのか」その意思を最大限に尊重してください。言葉での表現が難しい場合でも、その方の表情や行動から気持ちを汲み取り、代弁してあげることが重要です。
②家族・支援者との十分な話し合い
一人で抱え込まないでください。ご家族全員で、そして相談支援専門員などの支援者も交えて、オープンに話し合う場を持ちましょう。それぞれの立場からの意見を出し合うことで、より良い結論が見えてきます。
③将来を見据えた柔軟な選択
「一度決めたら変えられない」と思い込む必要はありません。ご本人もご家族も、年齢や状況によって変化していきます。その時々の状況に応じて、暮らしの形を柔軟に見直していく視点を持ちましょう。
最後に
もし、この記事をお読みいただき、「障がい者グループホームという暮らしの形に、少し興味が湧いてきた」「一度、実際の様子を見てみたい」と感じていただけたなら、ぜひ私たち千葉SMILEHOUSEへお気軽にご連絡ください。
私たちは、千葉県で障がいのある方々の「自分らしい暮らし」をサポートする障がい者グループホームを運営しています。
大切にしているのは、利用者様一人ひとりの笑顔です。
家庭的で温かい雰囲気の中、経験豊富なスタッフが、皆様の自立に向けた歩みを、きめ細やかに、そして力強くサポートいたします。
「いきなり入居を決めるのは不安…」
「うちの子でも、共同生活ができるかしら?」
「費用のことが詳しく知りたい」
どんな些細なご質問、ご不安でも構いません。
専門のスタッフが、皆様の心に寄り添いながら、丁寧にお答えします。
見学は随時受け付けておりますので、ぜひ一度、SMILEHOUSEの温かい日常を肌で感じてみてください。
あなたの、そしてあなたの大切なご家族の「これから」を、私たちと一緒に考えてみませんか?。
ご連絡を心よりお待ちしております。
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
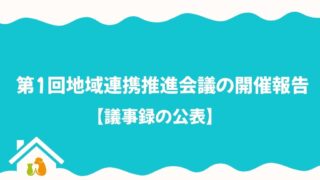 お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告
お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告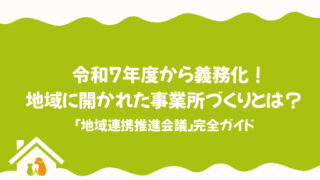 情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?
情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?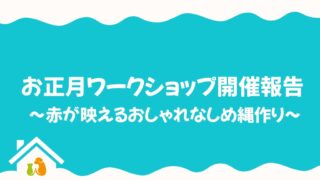 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告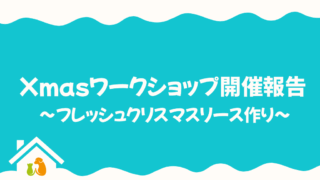 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告