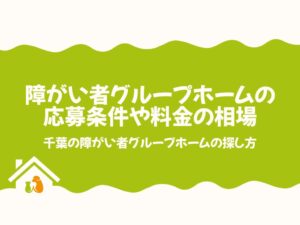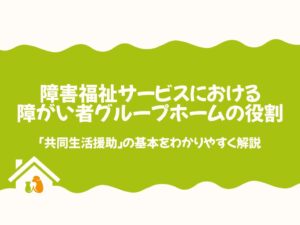軽度障害でも入居できる障がい者グループホーム|利用条件・サポート内容・実際の暮らしを徹底解説
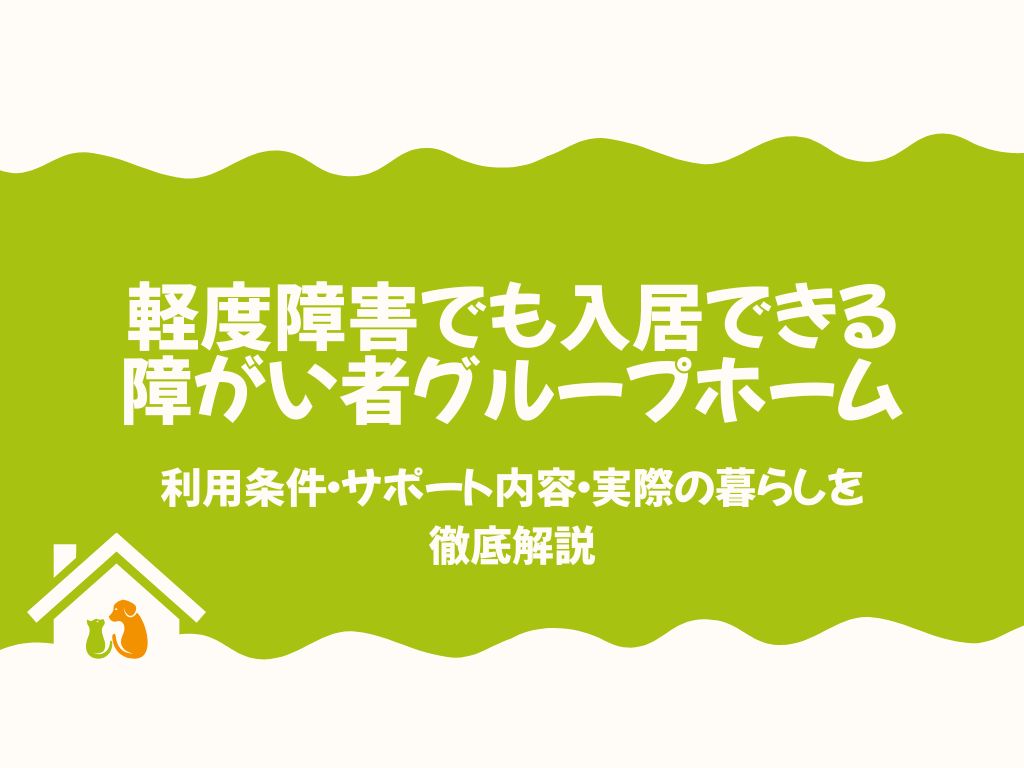
【はじめに】「軽度の障害だから…」と、一人暮らしや自立を諦めていませんか?
「親元を離れて自立したいけど、一人暮らしは少し不安…」 「日中は仕事に行けるけれど、食事の準備や金銭管理が苦手で…」 「軽度の障害だと、福祉サービスは利用できないと思い込んでいた…」
この記事を読んでくださっているあなたは、ご自身やご家族の将来について真剣に考え、様々な情報を探していることと思います。特に軽度障害のある方にとって、「自立」というテーマは、希望であると同時に大きな不安を伴うものかもしれません。
「障がい者グループホーム」という言葉を聞いたことはあっても、「重度の障害がある人が利用する場所でしょう?」というイメージをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。
ご安心ください。この記事を最後までお読みいただければ、そのイメージが変わり、新たな可能性が拓けるはずです。
▼この記事でわかること
①軽度障害でも障がい者グループホームを利用できること
②入居するための具体的な利用条件
③グループホームで受けられる安心のサポート内容
④費用や実際の暮らしのリアルなイメージ
私たちは、障害のある方とそのご家族に寄り添い、数多くの自立をサポートしてきました。その経験から、軽度障害のある方こそ、障がい者グループホームが「自立への確かな一歩」を踏み出すための最適な場所になり得ると確信しています。
あなたの「やってみたい」「変わりたい」という気持ちを、この記事が力強く後押しできれば幸いです。
【結論】軽度の障害でも障がい者グループホームは利用できます
まず、最もお伝えしたい結論から。 軽度の障害であっても、障がい者グループホームは利用できます。
「障害支援区分」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは障害の程度を示す指標の一つですが、区分が低い、あるいは区分認定を受けていない「区分なし」の方でも、入居可能な障がい者グループホームは数多く存在します。
むしろ、日常生活のほとんどは自分でできるけれど、苦手な部分だけをサポートしてほしい、という軽度障害の方にこそ、グループホームはピッタリの環境と言えるのです。
障がい者グループホームは、できないことをすべてやってもらう「施設」ではありません。あくまでもご自身の力を活かしながら、必要なサポートを受けて地域社会で暮らしていくための「住まい」です。
あなたの「自立したい」という想いを、夢物語で終わらせないための心強い選択肢。それが、軽度障害の方のための障がい者グループホームなのです。
1. そもそも障がい者グループホーム(共同生活援助)とは?
では、改めて「障がい者グループホーム」がどのような場所なのか、基本から確認していきましょう。
自立した生活を目指すための「住まい」
障がい者グループホームとは、正式には「共同生活援助」という障害福祉サービスです。障害のある方が、専門スタッフ(世話人や生活支援員)のサポートを受けながら、数人の仲間と共同で生活する「住まい」のことを指します。
最大の目的は、入居者一人ひとりがその人らしい自立した生活を送れるようになること。 そのため、食事や掃除、金銭管理といった日常生活の支援から、悩み事の相談、関係機関との連携まで、幅広いサポートが提供されます。
入所施設や一人暮らしとの違い
障がい者グループホームの位置づけを、他の選択肢と比較すると分かりやすいでしょう。
| 障がい者グループホーム | 入所施設(障害者支援施設) | 一人暮らし | |
|---|---|---|---|
| 目的 | 地域社会での自立 | 24時間体制の介護・生活支援 | 完全な自立 |
| 生活の場 | 一般的な住宅(アパート・一軒家) | 専用の施設 | 自由 |
| 自由度 | 比較的高く、日中は仕事等へ | 施設内のルールに基づく | 完全に自由 |
| サポート | 必要な部分を必要なだけ | 手厚く、常時介護が中心 | 基本的になし |
| 対象 | 地域での自立を目指す方 | 常時介護を必要とする方 | すべて自分でできる方 |
このように、障がい者グループホームは、手厚すぎる介護が必要なわけではないけれど、一人暮らしにはまだ不安が残る…という軽度障害の方にとって、まさに「ちょうどいい」選択肢と言えます。
グループホームの主な種類
グループホームは、提供されるサービス内容によって、主に3つのタイプに分かれます。
・介護サービス包括型: 主に夜間や休日に、そのグループホームのスタッフが食事や入浴などの介護サービスを提供します。最も一般的なタイプです。
・日中サービス支援型: 24時間スタッフが常駐し、日中も支援が必要な方に対応します。短期入所(ショートステイ)の機能も備えていることが多いです。
・外部サービス利用型: 日常生活の相談や支援はグループホームのスタッフが行い、入浴などの介護が必要な場合は、外部の事業所と契約してサービスを利用するタイプです。
軽度障害の方の場合、ご自身の状況に合わせて、主に「介護サービス包括型」や「外部サービス利用型」の障がい者グループホームを選ぶことが多いでしょう。
2. 【利用条件】軽度障害の方がグループホームへ入居するための具体的な条件
「自分も利用できるかもしれない」と少し希望が見えてきたところで、次に入居するための具体的な条件について詳しく見ていきましょう。軽度障害の方が気になるポイントを中心に解説します。
障害者手帳は必須?
原則として、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のいずれかをお持ちの方が対象となります。
ただし、自治体によっては、手帳がなくても、障害があることを証明できる医師の診断書や、自立支援医療受給者証などで代用できる場合があります。
「手帳がないから無理」と諦める前に、まずはお住まいの市区町村の障害福祉窓口や、後述する相談支援事業所に問い合わせてみることが大切です。
「障害支援区分」は必要?区分認定の流れ
ここが軽度障害の方が最も気にされるポイントかもしれません。結論から言うと、障害支援区分が「区分1」や「区分なし(非該当)」であっても、入居できる障がい者グループホームはたくさんあります。
そもそも障害支援区分とは? 障害支援区分とは、障害福祉サービスを利用する際に、どのくらいのサポートが必要かを判断するための全国共通の尺度です。区分1(支援の必要性が最も低い)から区分6(最も高い)までの6段階と、「非該当」があります。
区分がなくても諦めないで! 障がい者グループホーム(共同生活援助)の利用対象者は、障害支援区分を持っている方に限定されていません。市区町村が「共同生活を営むのに支障がない」と判断すれば、区分がなくてもサービスの利用が認められるケースがあるのです。
特に軽度障害の方は、区分認定調査で「非該当」となることも珍しくありません。しかし、それは「支援が必要ない」という意味ではなく、「グループホームという環境があれば自立できる可能性がある」と捉えることができます。
事業所によっては、区分がある方を入居の優先条件としている場合もありますが、まずは「区分がなくても入居できますか?」と直接問い合わせてみることをお勧めします。
対象となる障害の種類(精神障害・発達障害・知的障害など)
障がい者グループホームは、特定の障害に限定されるものではありません。
・精神障害(統合失調症、うつ病、双極性障害など)
・発達障害(ASD:自閉スペクトラム症、ADHD:注意欠如・多動症など)
・知的障害
・身体障害
・難病
など、様々な障害のある方が利用しています。 グループホームによっては、「精神障害のある方向け」「知的障害のある方向け」など、特定の障害に特化した運営をしている場合もあります。ご自身の障害特性に合った環境を選ぶことで、よりきめ細やかなサポートを受けやすくなるでしょう。
年齢制限について
原則として、18歳以上65歳未満の方が対象です。 ただし、65歳になる前からグループホームを利用していた方は、その後も継続して利用できます。また、特別な事情がある場合は、18歳未満や65歳以上の方でも利用が認められることがありますので、こちらも市区町村の窓口にご相談ください。
3. 【サポート内容】「自立」を支えるための具体的なサポートとは?
軽度障害の方が障がい者グループホームで受けるサポートは、「お世話」というよりも、自立に向けた「練習」や「後押し」といった側面の強いものになります。一人ひとりの「できること」を尊重し、「苦手なこと」を一緒に乗り越えていく、伴走者のような役割をスタッフが担います。
具体的にどのようなサポートが受けられるのか、見ていきましょう。
①日常生活のサポート
・食事: 栄養バランスの取れた朝食・夕食の提供。休日には、自分で料理の練習をすることもできます。
・掃除・洗濯: 共有スペースの清掃はスタッフが行い、個室の清掃や洗濯はご自身で行うのが基本ですが、やり方が分からない場合は丁寧に教えてもらえます。
・金銭管理: お給料やお小遣いの管理方法について相談に乗ってもらったり、一緒に計画を立てたりします。無駄遣いを防ぎ、貯金ができるようにサポートします。
②健康面のサポート
・服薬管理: 薬の飲み忘れがないように、声かけや確認のサポートを行います。
・体調管理: 「なんだか調子が悪いな」という時に相談でき、必要であれば病院への連絡や付き添いも行います。
・通院同行: 一人での通院が不安な場合、スタッフが付き添ってくれるので安心です。
③日中活動に関する支援
・多くの方は、日中は一般企業や福祉的就労(A型・B型事業所など)で働いています。
・仕事の悩みを聞いてもらったり、職場との連絡調整をお願いしたりすることができます。
・これから仕事を探したいという方には、ハローワークや就労支援事業所への同行など、就職に向けたサポートも行います。
④緊急時の夜間対応
・夜間に体調が急変したり、何かトラブルがあったりした際も、常駐またはオンコールのスタッフが迅速に対応してくれるため、一人暮らしにはない大きな安心感があります。
⑤コミュニケーションや対人関係の相談
・共同生活や職場での人間関係の悩みなど、一人で抱え込まずにスタッフに相談できます。他の入居者さんとの間でトラブルが起きた際も、間に入って調整してくれます。
これらのサポートは、すべてを強制されるものではありません。
あなたの意思を最大限に尊重し、「自分でやりたいこと」「手伝ってほしいこと」のバランスを取りながら、自立へのステップを一緒に考えていくのが障がい者グループホームの支援スタイルです。
4. 【実際の暮らし】グループホームでの生活をイメージしてみよう
「サポート内容は分かったけど、実際にどんな毎日を送るんだろう?」 そんな疑問にお答えするために、障がい者グループホームでの生活を具体的にのぞいてみましょう。
ある入居者さんの1日のスケジュール(平日・休日)
【平日の例(日中、作業所へ通うAさん)】
| 時間 | スケジュール |
|---|---|
| 7:00 | 起床・身支度 |
| 7:30 | 朝食(みんなでリビングで食べる) |
| 8:30 | 出発(「いってきます!」と作業所へ) |
| 9:00~16:00 | 日中活動(作業所で仕事) |
| 17:00 | 帰宅(「ただいま!」) |
| 17:30 | 入浴・自由時間(部屋でくつろいだり、他の入居者と話したり) |
| 18:30 | 夕食 |
| 19:30 | 自由時間(テレビ、趣味、明日の準備など) |
| 22:00 | 就寝 |
【休日の例】 休日は、平日の疲れを癒したり、自分の好きなことをして過ごす大切な時間です。
・午前: ゆっくり朝寝坊。溜まった洗濯物を片付ける。
・昼食: 自分で簡単な昼食を作ってみる。
・午後: 友人と出かけたり、一人でショッピングや映画を楽しんだり。グループホームの仲間やスタッフと一緒にレクリエーション(BBQやお出かけなど)に参加することも。
・夕食: みんなで夕食。
・夜: 趣味の時間やリラックスタイム。
これはあくまで一例です。日中の過ごし方も、生活リズムも人それぞれ。あなたのペースを大切にしながら、規則正しい生活習慣を身につけていくことができます。
プライバシーは守られる?個室と共有スペースについて
共同生活と聞くと、プライバシーが気になる方も多いでしょう。 障がい者グループホームでは、一人ひとりに鍵付きの個室が用意されているのが一般的です。一人の時間を大切にしたい時は、誰にも邪魔されずに自室でゆっくりと過ごすことができます。
一方で、リビングや食堂、浴室、トイレなどは共有スペースとなります。ここでは、他の入居者さんと交流したり、スタッフに相談したりと、人とのつながりを感じることができます。
「一人の時間」と「人とのつながり」。この二つをバランス良く保てるのが、グループホームの大きな魅力の一つです。
5. 【費用】気になる利用料金の内訳と活用できる補助制度
自立した生活を送る上で、お金のことは非常に重要です。障がい者グループホームの利用にかかる費用は、大きく分けて2つあります。
①障害福祉サービスの利用者負担額(国が定める費用)
②その他の実費負担(家賃、食費、水道光熱費など)
軽度障害の方の場合、特に2の実費負担がどのくらいになるのかが気になるところだと思います。
毎月かかる費用の内訳(家賃・食費・水道光熱費など)
グループホームで生活するために、ご自身で負担する費用の目安は以下の通りです。
| 費目 | 金額の目安(月額) | 内容 |
|---|---|---|
| 家賃 | 30,000円~60,000円 | 立地や部屋の広さにより変動 |
| 食費 | 20,000円~30,000円 | 朝夕の食材料費など |
| 水道光熱費 | 10,000円~15,000円 | 電気・ガス・水道代 |
| 日用品費 | 5,000円程度 | トイレットペーパーなど共有で使う消耗品費 |
| 合計 | 65,000円~110,000円程度 | ※家賃補助適用前の金額 |
これに加えて、ご自身の携帯電話代やお小遣いなどが必要になります。
家賃が軽減される国の補助制度(補足給付)
「合計金額を見て、ちょっと高いかも…」と感じた方、ご安心ください。障がい者グループホームの入居者には、国から家賃の一部を補助してもらえる「補足給付」という制度があります。
この制度を利用すると、月額1万円を上限として家賃が補助されます。 例えば、家賃が50,000円のグループホームに入居した場合、1万円が補助されるため、自己負担は40,000円になります。 (※生活保護や低所得世帯の方は、さらに手厚い補助が受けられる場合があります。)
市区町村独自の家賃助成制度
さらに、国からの補助に加えて、お住まいの市区町村が独自に家賃助成制度を設けている場合があります。これにより、自己負担額をさらに抑えることが可能です。
これらの補助制度を最大限に活用すれば、障害基礎年金の範囲内で十分に生活していくことも可能です。 詳しい制度の内容や申請方法については、グループホームのスタッフや市区町村の窓口が丁寧に教えてくれますので、遠慮なく相談しましょう。
6. 軽度障害の方がグループホームを利用するメリットと注意点
新しい環境に飛び込む前には、良い点(メリット)と、少し心構えが必要な点(注意点)の両方を知っておくことが大切です。
メリット
・安心できる環境で自立への準備ができる 一人暮らしで何かあったら…という不安から解放されます。スタッフの見守りがある安心感の中で、自分のペースで家事や金銭管理のスキルを身につけていくことができます。
・生活リズムが整い、心身の安定につながる 決まった時間に食事や起床・就寝をすることで、生活リズムが整います。これは心と体の健康を保つ上で非常に重要で、日中の仕事や活動にも良い影響を与えます。
・同じ境遇の仲間と出会える 同じように自立を目指す仲間がいることは、大きな励みになります。悩みを分かち合ったり、一緒に余暇を楽しんだりすることで、孤立を防ぎ、社会とのつながりを実感できます。
・ご家族の精神的・身体的負担を軽減できる ご家族にとっては、「親なきあと」の心配を軽減できるだけでなく、お子さんの成長を少し離れた場所から見守れるというメリットがあります。お互いが良い距離感を保つことで、より良好な親子関係を築けることも少なくありません。
注意点(デメリット)
・共同生活ならではのルールがある 完全に自由な一人暮らしとは違い、食事の時間や門限、共有スペースの使い方など、他の入居者さんと気持ちよく過ごすためのルールがあります。
・人間関係で悩む可能性 様々な個性を持つ人との共同生活なので、時には意見が合わなかったり、ちょっとしたトラブルが起きたりすることもあります。しかし、そんな時こそスタッフが間に入ってサポートしてくれるので、一人で抱え込む必要はありません。
・希望するグループホームに空きがない場合も 人気のグループホームは、すぐに入居できないこともあります。いくつかの候補を見つけて、早めに情報収集や見学を始めることが大切です。
これらの注意点は、事前によく理解し、見学の際にスタッフに質問したり、体験入居を利用したりすることで、入居後のミスマッチを最小限に抑えることができます。
7. ご相談から入居までの5ステップ
「グループホーム、本格的に考えてみたい!」と思った方のために、相談から入居までの具体的な流れを5つのステップでご紹介します。
STEP1:相談窓口へ まずはお住まいの市区町村の障害福祉課や、相談支援事業所に連絡してみましょう。「グループホームの利用を考えている」と伝えれば、専門の相談員が親身に話を聞き、必要な手続きや情報提供をしてくれます。
STEP2:グループホーム探しと比較・検討 インターネットで探したり、相談員に紹介してもらったりして、候補となるグループホームをいくつかリストアップします。立地、費用、雰囲気、サポート内容などを比較検討しましょう。
STEP3:見学・体験利用でミスマッチを防ぐ 気になるグループホームが見つかったら、必ず見学に行きましょう。実際の建物の様子や、スタッフ・入居者さんの雰囲気を肌で感じることが何よりも大切です。可能であれば、数日間宿泊する体験利用をしてみることを強くお勧めします。
STEP4:障害福祉サービスの利用申請 入居したいグループホームが決まったら、市区町村の窓口で障害福祉サービス(共同生活援助)の利用申請を行います。この時、サービス等利用計画案の作成も必要になりますが、相談支援事業所の相談員がサポートしてくれるので安心です。
STEP5:利用契約と入居開始 市区町村から「支給決定」の通知と「障害福祉サービス受給者証」が交付されたら、グループホームと正式に利用契約を結びます。そして、いよいよ新しい生活のスタートです!
8. 軽度障害の方のグループホーム利用に関する「よくあるご質問」
最後に、軽度障害の方やそのご家族から特によくいただく質問にお答えします。
Q. 日中、仕事をしていますが利用できますか?
A. はい、もちろん利用できます。むしろ、日中に仕事や作業所などの日中活動の場があることが、入居の前提条件となっているグループホームがほとんどです。
Q. 門限や外泊にルールはありますか?
A. はい、多くのグループホームで安全管理のために門限が設けられています。外泊については、事前に届け出をすれば可能な場合がほとんどです。ルールは事業所によって異なるため、見学の際に確認しましょう。
Q. どのくらいの期間、入居できますか?
A. 利用期間に定めはありません。数年間で一人暮らしのスキルを身につけて卒業していく方もいれば、終の棲家として長く暮らす方もいます。あなたの目標や希望に合わせて、柔軟に考えることができます。
Q. 将来的な一人暮らしに向けたサポートはありますか?
A. はい、多くのグループホームが、将来の完全な自立(一人暮らし)を目標としたサポートに力を入れています。貯金の計画を立てたり、アパート探しの相談に乗ったりと、卒業(退去)に向けた支援も行っています。
【まとめ】障がい者グループホームは、あなたらしい自立への第一歩を応援する場所です
ここまで、軽度障害の方が障がい者グループホームを利用するための条件やサポート、実際の暮らしについて詳しく解説してきました。
軽度障害だからこそ抱える、「できること」と「できないこと」のアンバランスさ。そして、「自立したい」という強い想いと、それに対する漠然とした不安。障がい者グループホームは、そんなあなたの心に優しく寄り添い、確かな自信を育んでくれる場所です。
①安心できる環境で、生活スキルを自分のものにできる。
②頼れるスタッフと仲間が、すぐそばにいる。
③経済的な負担を抑えながら、自立した生活が送れる。
一人で、あるいはご家族だけで悩みを抱え込む必要はありません。 この記事が、あなたの未来を照らす小さな光となったなら、これほど嬉しいことはありません。
千葉県で軽度障害に対応した障がい者グループホームをお探しなら、私たち「千葉SMILEHOUSE」にご相談ください。
私たちは、入居者様一人ひとりの「やってみたい」「こうなりたい」という想いを大切に、きめ細やかで温かいサポートを提供しています。アットホームな雰囲気の中で、あなたのペースで、あなたらしい自立への道を一緒に見つけていきましょう。
「まずは話だけでも聞いてみたい」 「一度、雰囲気を見てみたい」
そんな気軽な気持ちで、ぜひ一度お問い合わせください。 あなたからのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
投稿者プロフィール

- スマイルハウスのスタッフ森です。施設内の様子など定期的に投稿していきます。
最新の投稿
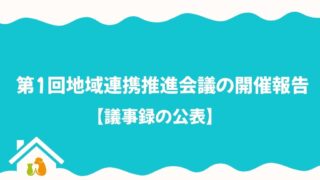 お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告
お知らせ2026年1月29日【議事録公表】第1回 地域連携推進会議の開催報告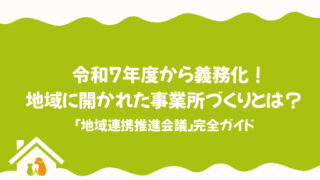 情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?
情報発信2026年1月15日令和7年度から義務化!「地域連携推進会議」完全ガイド:地域に開かれた事業所づくりとは?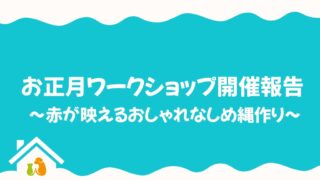 情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告
情報発信2026年1月1日お正月ワークショップ開催報告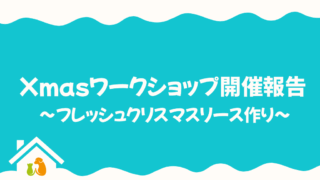 情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告
情報発信2025年12月18日Xmasワークショップ開催報告